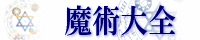 〜最下級召喚獣〜 5 〜最下級召喚獣〜 5 |
トリスは眠れない朝を幾日も迎えていた。
ダイはこの数日戻らず、エカティの消息もいまだ不明のままだ。
不安はある。むやみに動くことが得策でないとも思っている。
エルバイト家の人は、何も言わずにただ娘が帰ってくることを願っていた。
明日は卒業認定試験の日になる。今日中に見つけ出せなければ、エカティの魔術師としての将来は閉ざされてしまうだろう。
トリスは何度か召喚獣を呼び出す法陣を書いて、ダイからの返答を待っていた。
だが、手ごたえが全くない。
ダイは下級とはいえ魔族である。全く反応がないということがおかしいのだ。
「トリス、あなたに電話よ」
部屋の扉がノックされ、告げられた言葉は意外なものだった。
「はい。いま行きます」
「なにかとても騒がしいところにいるみたいで、相手の名前がよく聞こえなかったのだけど、女の方みたい」
困ったように微笑み、エルバイト家の夫人は小さな端末をトリスに手渡す。
個人的な用事と思って気を遣ってくれたのだろうか。
心当たりのないトリスは「すいません」と言って、その端末を受け取った。
「もしもし?」
確かに端末からもれ聞こえる音は、多くの人間が行きかう雑踏のような雰囲気を感じさせた。
「トリス? 突然ごめんなさい。私、ロゼット」
それは予想もしない相手からだった。
「ロゼット? きみ、いつ意識が戻ったの? 体は大丈夫? エカティも随分心配していたんだよ。きみの声を聞けば安心する……」
「その話はあとにして。母さんから大体の状況を聞いたわ。意識があるうちにどうしても伝えておきたいことがあるの。今から私が言うこと、ちゃんと覚えておいてくれる?」
苦しそうな声のなか、ロゼットはトリスを遮り一方的に話を始めた。
それは、トリスも初めて聞くどこか他人事のような知らない話だった。
しばらく話すとロゼットはほぼ言いたいことを終えたのか、周囲の喧騒を遮ってこう付け加えた。
「ずっと言えなくてごめんなさい。でも、油断しないで。召喚獣は万能じゃない。召喚士の能力がどんなに高くても、いつだって傷ついて死んでしまう可能性はあるんだから」
遠くで「早く病室へ連れて行きなさい」という怒鳴り声が聞こえてくる。ロゼットが無茶を承知で伝えてくれたことを、無駄にするわけにはいかない。トリスは答える。
「わかってるよ、大丈夫。だからどうか謝らないで」
ロゼットからの返答はなかった。答えなかったのか、あるいは聞こえない所まで連れられていった後だったのか、おそらくは後者だろうとトリスは思った。
端末を閉じると、トリスは部屋を飛び出した。
「おばさん、ぼくちょっと出かけてきます」
持っていた端末を手渡すと、驚いたような顔がトリスを見つめた。
「どこにいくの?」
卒業認定最終試験の前日は、学校自体が閉鎖される。
試験準備のために教師以外の誰にも立ち入ることを許されないのが常だ。
「学校。審問会にかけあってきます」
「入れないわよ?」
「普通ならね。でも、今のぼくなら扉は開く。ぼく一人なら、きっと。心配しないでください。エカティも連れて戻ってくるから」
強い確信を感じさせるトリスの言葉は、制止するまもなく飛び出した少年の残滓のように、エルバイト家の夫人の心に希望という暖かいものを残していた。
ダイは床に描かれた魔法陣のなかにいた。
出ようとしてもヤグがそれを邪魔する。
もともと魔族としての格が違う。向き合っているだけでもかなりの恐怖だった。そして、法陣の中心ですすり泣く同属の姿が、ダイを縛る枷にもなっていた。
「ゴメン。本当にゴメンね、ダイ」
「知らなかったんだから仕方ねえよ」
この法陣に押し込められてから、数日は経っているはずだった。日にちの経過がはっきりしないのは、この部屋に差し込む光が欠片もないこと、始終ヤグという火蜥蜴に見張られて気が抜けない状態であることも手伝い、焦る気持ちを抑えるだけで精一杯の状況だ。
ボウ、と音を立ててヤグが火炎を吐き出した。
欠伸とともに出ただけで、鉄鼠にむけられたものではない。だが、円陣の中心にいる鉄鼠たちはそれだけでも十分に震え上がった。
鉄をも砕くと言われる前歯が半分溶け、その体毛もあちらこちらに焦げがある。爪は折られたのか中途半端な長さで不揃いに、本来は長くあるはずの髭や尻尾も焼ききれたように黒い傷跡で切断されている。
ダイを含めてこの場にいる鉄鼠三匹は、そうした傷跡を体のどこかに多かれ少なかれ作っていた。そのなかでダイは一番軽症だった。一番拘束時間が短いということもあるが、ヤグの炎はダイの体を思ったほどに傷つけられずにいた。それは、ダイが首にまく赤いリボンの効力でもある。
正式なる召喚獣の証は、それを持たないヤグの炎を遮るのに十分だった。
「なんだ、結構頑張ってるんだね。予想外だよ」
突然降りかかる少年の声に、ダイは視線を上げた。
ダイの主と同じ年齢の少年は、笑顔でその先を続ける。
「やっぱりそのリボン、邪魔だよね。ほどけないから仕方ないけど、本来、鉄鼠なんかが火蜥蜴に対抗できるはずないのにさ」
「だからなんだって言うんだよ」
「やだなあ、これでも褒めてるんだよ。健闘してるって。でも、お前がいる限りトリスティン・クロソライトの名がぼくの前から消えなくて目障りなんだよ」
少年は椅子にもたれかかり、改めてダイを見つめていた。
「最初にやってのけたってだけで、最年少の記録があるってだけで、こんな下級魔族くらいでぼくの前をいってほしくないんだ。それにさ、彼ならもっと上級魔族を呼び出せるはずだろう? お前を還してしまえば結構いい好敵手にもなれそうなんだよ。そういう意味では少し期待もしてるんだ」
「おいらを送還なんて、トリスが承知しねえよ」
「そう? 随分な自信だね。でもあの子、エカティ・エルバイトだっけ? あの子の将来がかかっていたらどうかな」
くすくすと笑いながら、細く赤いリボンを指先でもてあそび、ノット・ハウライトは呟いた。
「幼馴染の女の子が大事か、下級魔族の召喚獣が大事か、それとも両方とも見捨てるか、それはそれで見物だよね」
召喚獣の証はヤグの首ではなく、ノットの指先で小さな輪を作っていた。
ダイがいる魔法陣は召喚陣だ。中央ですすり泣く同属はノットに召喚されたダイとは違う他の鉄鼠だ。
ヤグを召喚陣に入れている間なら、召喚獣の証は取り外しができる。そうして新たに召喚した鉄鼠に召喚獣の証であるリボンをつけ、ノットはダイの仕業に見せかけた事件をいくつも引き起こしたのだった。
召喚陣にこんな裏技があることを知る者は少ない。
ノットの持つ知識は紛れもなく本物だ。召喚士としても相当な使い手だろう。
それでも、と思う。
「トリスはおいら達を助けてくれるさ」
「ふーん、どうやって?」
「そんなこと知らない。でもトリスなら、あのそばかす女のことだって絶対見捨てない。おいらの事だって送還したりしない。お前とトリスは違うんだからな」
「そりゃそうだね。ぼくなら鉄鼠を召喚獣になんて真っ平ゴメンだ」
投げかけられる侮蔑の視線は、ダイにとっては日常茶飯事のことだ。
人間界に限らない、魔界にいたときも同じことだ。
最下級と呼ばれる魔族。魔力も特殊な能力があるわけでもない。一族が生きるために己の身を差し出す火鼠よりも下の存在だ。
魔界には差し込む光がない。光を求めて魔族は異界よりの召喚に答える。
召喚先の異界で住獣権を得られると、その世界で取り込んだ光を一族に還元することができる。
光は生きるために必要なものだった。
どんなに頑張っても、鉄鼠を召喚する異界はない。稀に使い魔として使役されることもあるが、それでも絶対量が不足している。死ぬためだけに生まれる子供がいる。半数以上が成獣するまで生き残ることさえできない。召喚獣に召されることは、一族の存亡をかけた悲願だった。
だから、ノットに召喚され、いいように使われてしまった同属の気持ちが痛いほどわかる。責めることなどできはしなかった。
初めての異世界に戸惑うダイに、トリスは笑って言ってくれた。
「この世界にきみは一匹しかいない。ぼくも一人だ。同じだね」
トリスとだって、最初から今のような関係を築けたわけではなかった。
人間界のルールを知らずに何度も失敗をした。迷惑をかけた。そのたびに送還されるのかと怯えるダイに、トリスは言ったのだ。
「知らないことは恥ずかしいことじゃない。失敗することも同じだよ。召喚獣としての知識がないのは仕方がないことだよ。でも同じ失敗を二度犯してはダメだよ」
周囲はダイが失敗するたびに口を揃えて「送還」のことを口にする。ダイも、はじめはトリスの顔色を伺うことばかりだった。
トリスの放つ光は拙い魔法陣からでもダイをひきつけた。
そばにいると、ダイでもわかる。
トリスに自分は相応しくない。誰もが言うそのことはきっと正しい。
ダイは小さな手のひらを握り締める。
自分の主は、きっと自分を見捨てたりはしない。
主と呼んだことは一度もないけれど、役に立てたことだって一度もないけれど、今までだってずっと見捨てずにいてくれたのだから。
「おいらが信じている。それだけで十分理由になるんだよ」
ダイの緑の大きな目が、ノットを正面から見返した。
審問会の扉は、トリスの要請に応える形で開かれた。
「行方不明になったのですか?」
「はい。申し訳ございません」
驚く審問会のメンバーを前に、トリスはただ頭を下げる。
「それでは今後、事件が起こっても疑いを晴らすことができませんね」
戸惑うほかのメンバーとは違い、マグレガー・メイザースは天気のことでも語るかのように言ってのける。
「いいえ、それは違うと断言できます。なぜなら、私の召喚陣にも答えられない場所に彼がいるからです」
召喚士に応えない召喚獣はいない。審問会のざわめきは更に広がる。
「理由はわかりますか?」
「いいえ、全く。ですからこうしてお願いに参りました。私に召還陣の許可を与えてください」
召喚ではなく、召還。
異界から呼び出すのが召喚なら、己の召喚獣を呼び戻すことを召還という。
新たに招くのではなく、刻んだ印を引き寄せるものだ。
未成年の召喚獣に与えられるリボンには片側に五芒星、もう片側には家紋が刻まれる。
召喚獣には貴重種が多い。行方不明になることはまずありえないので滅多に行われないが、召喚獣を召還する権限は召喚主にのみ与えられる。
魔族の住獣権は五芒星で証明される。ダイはまだトリスの召喚獣である。誰かがダイを無理やり魔界へ送還していたとすれば、ダイに二度と住獣権は与えられない。一度でも住獣権を得た魔族は、二度と同じ世界に住獣権を得ることができないのだ。だが居場所が不明というだけのいまなら、ダイのもつ五芒星と家紋に召還をかけることは可能となる。それを行えるのはダイの召喚士であるトリスただ一人だ。
本来、『青銀』レベルの学生が知りえる情報ではない。情報源はロゼットだった。
審問会メンバーの一人が溜息を吐いた。
「鉄鼠でしょう? 召還をかける価値があるのかね?」
「ぼくにはその価値があると思っています。なぜならダイは、現在行方不明のエカティ・エルバイトの捜索を依頼していて同じく姿が見えなくなったのです。ダイのいる場所にエカティ・エルバイトがいる可能性が高いからです」
「宜しい。許可を出しましょう」
マグレガー・メイザースは誰よりも先に応えた。最高指導者の決定に、他の審問会のメンバーは口を閉ざす。
確かに、鉄鼠が目的ではなく、その傍らにいる可能性がある少女の探索と言われたなら反対の理由がない。
「あなたにこれを貸し与えましょう。これには召還の法陣が記載されています」
差し出されたのはグリモワールという稀少な魔術書だった。『ソロモンの鍵』と呼ばれるその魔術書は、数冊しかないといわれる貴重な書物だ。
「必ず皆で無事にもどり、私にこれを返しにきてください」
マグレガー・メイザースはトリスに魔術書を手渡した。無表情だとばかり思っていた彼の目じりが、少しだけ下がって見える。
トリスは深く一礼し「失礼します」と言うと審問室を飛び出していった。
「大達人!」
周囲の魔術師が非難めいた声を上げる。
「なんでしょうか?」
「あんな子供に召還などという危険な陣を書く権利を与えるのは、いくら大達人の称号をもつあなたでも早計だと思いますが。それに、禁書を渡すとは……」
「私はクロソライト家の当主に請われて禁書を貸し出したのです。なにか問題がありますか?」
「あれはまだ『青銀の夜明け学校』の生徒にすぎません」
その一言に賛同する者のほうが多かった。だが、マグレガー・メイザースは平然と答える。
「それでは、我々は彼を都合の良いときだけ当主として大人の責任を問い、都合の良いときには学生として遇することになりますね。そんな勝手は認められません」
「しかし!」
「お忘れではないでしょうね、皆さん。彼は私を後見でなく、補佐でなく、補助に選んだのです。後見と補佐と補助の違いはお分かりですよね。どれほど幼くても彼がクロソライト家の当主です。彼が当主としての責務を果たす以上、我々も彼を当主として扱わなければならない。違いますか?」
後見ならトリスティン・クロソライトは当主としての責務をある一定年齢になるまで免れる。それは、後見人の同意がなければ当主会での議決権を行使できないからだ。
補佐は当主の決定した重大事項をとどめる程度の権限を持つ。
補助とは後見よりも補佐よりもずっと権限がない。助言することはできるが、その意見を聞く必要がないものだ。だからこそ、重要な決定事項の全ての責任は、補助人ではなく、当主自ら背負うことになる。
最後の身内を亡くしたあの日、トリスティン・クロソライトはクロソライト家の新当主になることを選んだ。
教師の誰もがダイオプティースの存在を疎ましく思っていながら、強制送還できなかったわけはここにある。
トリスティン・クロソライトがクロソライト家当主として全ての被害を弁済し頭を下げ続けたからこそ、送還という処置に強制力を持ち得なかったのだ。
「クロソライトの家紋は封じられていません。彼が当主となることを選んだからです。家紋と家名を背負うということは、相応の責任も負うが、相応の権利も得るということです。ましてや卒業認定試験直前の構内に、一学生としてのトリスティン・クロソライトに立ち入る権利はありません。彼はここにクロソライト家当主として現れた。だからこそ私達は今日、請われた彼に会う必要があったのですよ」
マグレガー・メイザースの言葉に反論できるものはいなかった。
魔術のなかでも、法陣を描く場は限られている。
校内でなら専用の法陣室というものがある。だが、本来立ち入り禁止の場に、生徒の一人でもあるトリスが、これ以上留まる理由にはならない。
『青銀の夜明け学校』を出たトリスは、日の沈みかけた空に視線を移す。
時間はあまり残されていない。法陣の失敗は許されない。
少し考えて、トリスは自宅へ向かった。エルバイト家の隣にある、本当の自宅でなら、誰の邪魔も入らず、法陣も安定するだろう。
あそこならダイの新居でもあり、エカティの記憶にもある場所だ。
両者に共通する場所であるほうが成功率が高くなる。
トリスは自宅へ駆け込み、リビングの食卓を力任せに壁際まで押し寄せた。
床にある程度の空間ができる。そこに、魔術書にある通り、忠実に法陣を写し取っていく。法陣はなにか一つでも欠けていれば効力を発揮しない。トリスは慎重に確認し、法陣の不備を埋めていく。
キキッと小さな鳴き声にトリスは視線を泳がせた。
小さな白いハツカネズミが、不安そうにトリスを見上げる姿を見つけると、トリスはそのハツカネズミの前にしゃがみこむ。
「大丈夫だよ、エリザベス。ぼくがダイを見つけるまで、法陣を消したり詠唱の邪魔はしないでね」
キュウと一声鳴き、白いハツカネズミは壁際に寄せられた机の上に駆け上がった。それを確認し、トリスは魔術書に視線を移す。長い呪文が数ページに渡って書かれてある。一度はじめてしまえば、中断することも間違えることも許されない。
「成功できるように、エリザベスもそこで祈っていてね」
そして、長い詠唱の時間が始まった。
どれほどの時間が経ったのだろう。
ダイは怯える同属を宥めつつ、ヤグを向かい合っていた。ノットは帰宅する際、ヤグの首に召喚獣の証を結わえて言った。
「見張りは明日までだからな。そのあとは好きにしてもいいぞ」
火蜥蜴は小さな火炎を吐いて召喚士に応える。
同じ召喚獣として証を持つならヤグのほうがどうしても優勢だ。細長い舌をちろりと出し、ヤグは鉄鼠達を見つめていた。そこには捕食者としての愉悦すら感じる。
魔族は基本、異界では自分よりも下位魔族の魔力を吸い取るものだ。どれほど下級であっても魔族である以上、鉄鼠にも魔力は備わっている。微々たるそれをなくしたなら、魔界に戻ることも叶わず、異界の地で異端の存在として生涯を終えることになってしまう。
同属を背に庇うように、ダイはヤグの前に立ちふさがっていた。
召喚獣同士、片方がどれほど上位であっても無益な殺傷は許されない。それは建前だ。
魔界の上下関係は異界でも同じ効力を持つ。ただ、召喚士という存在がそれぞれの背後につくため、容易にならないというだけの話だ。
のそり、とヤグが動く。ダイは反射的に身構えた。
敵わない、恐ろしい、逃げ出したい。
本能は生命の危機を告げるが、背後のぬくもりがそれを許さない。
自分が退けば、ノットに召喚された同属はヤグに食われてしまうだろう。ヤグが容易に手出しできないのはダイだけなのだ。
そのときだった。ダイの首にまかれた赤いリボンが微かに光る。
気付いたのはヤグが最初だった。
召喚陣は常に仄かに光り存在を知らしめている。その光が反射したのだろうか、と思い直す。だが、次にはダイにも認識できるほどにリボンが光った。
「なんだ、これ」
ダイは自分の喉もとで光るリボンをじっと見つめた。
リボンの裾に刺繍された五芒星がよりいっそうの輝きを増す。同時に仄かでしかなかった召喚陣が光り始めた。淡く緩やかに燐光のような虹色を放つ。それは召喚陣の発動する合図だった。
「お前ら、陣の中央に立て。帰れるぞ」
火蜥蜴と対照の場で震えている鉄鼠にダイは叫んだ。正式な住獣権を持たない彼らは召喚陣から出ることができないのだ。
「どんなに火蜥蜴が怖くても、あの場所で待て。あいつはおいらが引き受ける。そんなに持たないだろうけどさ」
「でも……」
「自分で召喚陣くぐって人間界まで来られたんだ。行けるよな」
彼らの返答を待たず、ダイはヤグの前に進み出た。
ヤグは軽く首を振る。それは退けと言っているように見えた。
「イヤだ。退かない」
ありったけの勇気を振り絞ってダイは火蜥蜴と対峙した。
五芒星が更に光を増し、ノットが描いた法陣は効力を発揮しはじめた。
小さな光がいくつも宙に舞う。半円の球体が法陣を覆う。
このなかで自由に動けるのは、召喚士に招かれた契約を持つ召喚獣だけだ。
ヤグは狙った獲物を逃すものか、というようにダイの脇をすり抜けようとした。
その背にダイは噛み付いた。
鉄の歯と爪を持つ鉄鼠の歯は、遮る鱗すらないヤグの柔らかな背に大きく食い込んだ。
ヤグの尻尾に業火が灯る。
火蜥蜴の放つ火炎はダイの半身を炎で包み込んだ。
熱さと痛さのあまり、無茶苦茶に振り回した爪がなにかを引っ掛け、そして確かな手ごたえをダイは感じた。
渾身の反撃はそれまでだった。
ヤグが全身に放った熱でダイの歯が半分溶け、ダイはヤグから振り落とされる。
そのとき、召喚陣の光が突然消えた。中央にいた同属の鉄鼠の姿はなく、法陣のあとにはヤグとダイだけが残されている。
怒りに満ちた火蜥蜴の瞳が、最後に残された鉄鼠に向けられた。ダイは流石に死を覚悟した。
本来敵うはずもない火蜥蜴に向かったのだ。同属を逃がせただけでも上出来なくらいだ。
「なにしてるんだ、お前ら」
聞き覚えのある声がした。朦朧とした意識のなか、ダイは自分の体がふいに軽くなったような記憶を最後に意識を失った。
浮かび上がった映像は、見たことのある風景だった。
月に一度通う『黄金の夜明け学校』敷地内にある旧校舎。二階の中央にある部屋。法陣のなかでヤグと対峙するダイの姿。
トリスがもてる全ての力を法陣に注ぐと、不意に映像が途切れてしまった。
「エリザベス、留守番頼むね」
トリスは魔術書を机の上に投げ、駆け出しながら、白いハツカネズミに声をかけた。返事は必要ない。
彼女はいつでもあの家でダイの帰りを待つだろう。
既に暗い夜道を、トリスは走り続けた。
トリスの苦しかった毎日を、ダイは変えてくれた。
エルバイト家の人達は親切で、他の大人たちも身寄りをなくした自分を案じてくれた。それでも、周囲の哀れむような視線はトリスの心に見えない傷を残していった。
「可哀相な子なのだから」
そういう言われるたび、なにか反論したい気分になる。でも、自分の立場でそれは許されない。確かに庇護者が必要な年齢であったのだから仕方がない。
身寄りがいなければ哀れまれるのだろうか。それは懸命に生きる自分に惨めな姿でいることを要求している言葉に思えた。
両親の死も、祖母の死も悲しかった。一人残されたとき、誰よりも早く大人になりたいと思った。勉強もした。エルバイト家の人達に好かれる努力もした。それでも決して消えない哀れみの視線は、いつになってもトリスにつきまとう。
ダイが召喚陣から這い出てきたのは、そんな毎日に飽いていたころだ。
生意気で、なにを仕出かすのかわからなくて、ダイが来てからトリスは頭を下げてばかりだった。正直、送還したほうが良いのかもしれないと思ったこともある。
よく食べ、よく喋り、自由気ままに行動するダイが、一つだけ忠実に守ってきたことがあった。
朝、トリスが目覚めると、枕の横で必ず丸まっているのだ。
前日に姿が見えなくても、寝ている姿だけでその日も一日行方不明であっても、必ずトリスが目覚めるとき、ダイの小さな呼吸と微かな体温をそこに感じるとき、「まあ、いいか」と思えてしまう。
ダイはトリスを決して哀れまない。この人間界において異端な存在でありながら、誰よりも生きることを謳歌しているように見える。
「ダイはいつも楽しそうだね」
「おうよ、楽しいぜ。おいらは楽しいことを見つけるのが好きなんだ」
頬をふっくらと膨らませて笑うダイを見ているのが好きだった。
魔力もない、特殊な能力もない。けれど、ダイといると元気になれる。それだけでトリスには十分だった。
「いつかぼくも、おばあちゃんに負けないくらい強い魔族を召喚するんだ」
自分の召喚獣と戯れて宣言する孫に、祖母は言ったものだ。
「召喚獣の魔力なんて、そんなに関係ないもんだよ、トリス」
祖母の召喚獣は鳳凰で、希少種だと言われていた。祖母は孫の子守相手によく鳳凰を呼び出していたので、トリスにとって召喚獣はとても身近なものだった。
「一番初めに応えてくれた子が、案外、自分に一番必要な相棒なのかもしれないね」
「なんで? 最初の子って普通、一番弱いんでしょう?」
「確かにそうさ。召喚士の能力に比例するんだもの。でもね、今でも思い出すのは最初の子のことばかりだよ」
その理由は何度尋ねても教えてくれなかった。
あのときの祖母の気持ちが今ならなんとなく理解できる。
今のトリスに必要なのは、魔族が持つ魔力でも、特殊な能力でもない。
自分だけを頼りに生きる存在を守ることで得られるなにかが確かにある。
だから、どれほど迷惑をかけられても見捨てられない。
『黄金の夜明け学校』はその角を曲がると正面に見える。トリスは苦しくなる息を整え、ラストスパートをかけた。
「そろそろ目を覚ませ、鉄鼠」
耳元で風の音がする。全身がとても寒い。ダイはうすぼんやりと瞳を開く。
見たことの無い風景が眼下に広がっていた。
見上げたことしかない校舎が自分の足より下にある。半日かけて駆けてきたここまでの距離が一望できる。
「ウギャー、なんだ、これ」
じたばたと体をよじると、「それ以上暴れると落とす」という声が聞こえてきた。そして、自分の体を両足で掴み飛んでいる風魔鳥の存在に気付く。
「落とすなよ、モン・スー。おいらイチコロで死んじまう」
召喚獣講義で見知ったマルクの召喚獣は、ダイを抱えて飛んでいた。
「おいら、助かったんだな」
ポツリとダイは呟く。
「そうだ、そばかす女。あいつも助けなきゃいけないんだよ。モン・スー、悪いけど引き返してくれないか?」
「あの少女であれば、我が主が救出した。心配ない」
思わず安堵する。そして、結局今回も役に立てなかった自分に気付き、思わず笑ってしまった。
「おいら、いつになったらトリスの役に立てるんだろう」
モン・スーは無言で翼を動かしていた。
役に立ちたいと思いつつ、全てが裏目に出てしまう。今回も、光り輝くリボンの五芒星に、トリスの存在を感じ取ったからできた行動だ。自分ひとりでは絶対に動くことすらできなかった。
「もっと力があればいいのに」
言っても仕方のないことだ。わかっていても思わず口走る。
「力とは、魔力のことか?」
「いいや、そんなの願っても絶対無理だもん」
魔族は総じて生まれたときにその魔力は決まっている。あとから加えることも減らすこともできはしない。唯一方法があるとすれば、異界にて自分より下位の魔族から吸い取ることだけだ。
だが、最下級の鉄鼠にはその相手すらいない。
欲しいものは、もっと別の違うものだ。上手く説明できないけれど、ダイはそう思った。
「そういえば、モン・スー。おいらをどこへ運んでくれているんだ?」
「汝の主のもとまで。汝の足では夜が明ける」
「それはそうなんだけど、断言されると嬉しくねえぞ」
「失礼した」
「いいや、助かるよ。マルクにもお礼言っておいてくれよな」
クウ、と風魔鳥は困ったように一声鳴いた。
「今回は主の命令ではない。面白いものを見せてもらった。遅まきながら我より汝への結婚祝いである」
ぽん、とダイを空中に放り出し、モン・スーは鳴いた。勢いよく落下しながら、ダイはその真下にトリスの姿を見つけて思わず声を出す。
「トリス、おいらのお迎えか?」
伸ばされる彼の手が、自分の体を受けて止めてくれる。ダイはそれを信じて疑いもしなかった。
マルクに連れられて出てきたエカティとトリスが出会うのは、その少しあとになる。
|
|