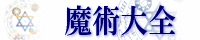 〜最下級召喚獣〜 4 〜最下級召喚獣〜 4 |
エカティが目を覚ますと、見たことも無い部屋の中にいた。両手両足を縛られ、床に転がされている状態で、まるで無造作に放り投げられたような格好である。
「なに、ここ。私、なんでこんな場所にいるんだっけ」
ぼんやりとした頭でゆっくりと記憶を辿る。
トリスのことを心配してきたという少年にあったのだ。彼は確かトリスの知り合いだと言っていた。エカティのこともトリスから聞いて知っていたと言う。
いろいろな話をした。今回の出来事がメインではあったが、トリスとダイのことについてはこと細かく話してしまった気もする。
ああ、そうだ。始業のチャイムに気を取られて振り向いた瞬間、首筋に衝撃を受けたのだ。
室内を見回そうと首を持ち上げた途端、首の後ろ、付け根のあたりがひどく痛んだ。その痛みでより意識がはっきりとする。
窓の外は既に暗く、気を失ってから随分と時間が経っていることが知れた。
帰らなきゃ、みんなが心配してる。
背後で結ばれた拘束を解くため、適当に手首をひねる。だが、拘束具が更に手首を締め付ける感じはあっても、解ける気配はない。
「驚いた。もう気がついたんだ。あの薬の量だと、あと半日は意識がなくてもおかしくないのに。さすがエルバイト家の一員って言ったほうがいいのかな」
静かな声が頭上で響く。それはエカティを訪ねてきた少年の声だった。
「あんたね、なんでこんなことするわけ? 私になんか恨みでもあるの?」
「ないよ、君にはね」
「だったらこれはずして、私を家に帰してよ」
「それはできないよ。そんなことしたら、ぼくの目的が達成できないんだもの。それに、きみにとっても決して悪い話じゃないと思うんだよね。ぼく達、利害は一致してるんだよね」
ゆっくりと近寄り、少年はエカティの前にかがむ。
「協力してくれるっていうのなら、はずしてあげてもいいよ。でも、無断で帰ったり、ぼくから逃げることは許さない」
「まず、私を起こして、協力とやらの内容を聞かせてよ。話はそれからじゃないとできない。私、こうしてあなたに見下ろされていることが不愉快なの」
一瞬驚いた顔をした少年は「いいよ」という言葉と共にエカティの上半身を即座に起こす。
「これで良い?」
「まあ、いいわ。それで、協力ってなに?」
「ダイオプティースを魔界へ送還する。そのためにも、きみには囮になってもらいたい。きみに危害を加えるつもりはないよ。ぼくの邪魔さえしなければね。きみだって、あのネズミが目障りなんだろう? いい話だと思うんだけど」
「確かに良い話ね。願ってもない話よ。でも、残念だわ。あのネズミは私のために動かないわよ?」
「そりゃそうだろう。最下級魔族であろうと能無しであろうと、あれでも召喚獣なんだ。召喚士の言うことしか聞かないよ。確かにあの鉄鼠は誰のためにも動かない。でも、召喚士であるトリスティン・クロソライトならどうだろうね」
エカティは正面にいる少年をじっと見た。優しげな物腰と浮かべる笑顔に人を拒む要素はない。それは本能が知らせた危機だったのかもしれない。この少年は危険だ、とエカティは瞬時に判断した。
「トリスが狙いなの? トリスだって私のために動くとは限らないわ」
「そんなことないだろう、謙遜してるの? ただ目障りなだけで、彼をどうこうしようとは思っていないよ。そうだな、強いて例えるなら、きみがダイオプティースを目障りなネズミだと思っているのと一緒ってとこかな?」
一緒にしないで、と思いはしたが、口にするほど愚かではなかった。
「別に彼が動かなければそれでも良いんだ。自分が世話になっているエルバイト家の娘が自分のせいで『青銀の夜明け学校』を卒業できなかった、っていう事実が残るだけでも、ぼくとしては大成功なんだよね」
彼に言われて気付く。
卒業認定試験までは数日しかない。あの試験を受けられなければ、魔術師への道は閉ざされてしまう。
「イヤよ。私は治療士になるのが夢なんだもの。あなたの話に加担すれば、自分の夢を捨てることになってしまうじゃない」
「そう。じゃあ残念だけど、しばらくそのままで我慢していてよ。卒業試験が終わったら、絶対に帰してあげるから」
さして嬉しくもない彼の提案を、拒否する権利はエカティになかった。とん、と軽く体を押され、気がつくとエカティの顔の横には床があった。
「あんまり暴れると、跡が残るよ。その縄って少し特殊で、もがけばもがくほど締め付けるようにできてるんだ」
エカティはたた一つ、自由に動く視線を動かして元凶となった少年を見上げる。
「あなたの名前くらい聞いておくべきだったかしら」
「教えるほどのものじゃないよ」
肩をすくめて少年は立ち去る。戸が閉まる音が背後で響いた。エカティは唇をかみ締めて、こぼれそうになる涙を懸命にこらえていた。
その場所は見知ったところであったが、ダイの足では半日ほどかかる。
ネズミ網からの知らせは、意外な場所を示していた。
『黄金の夜明け学校』旧校舎。それはトリスが召喚獣講義を受けに行く『黄金の夜明け学校』の敷地内にある。
エリザベスに言われてダイは直接この場所へやってきた。
トリスに報告するよりも、ダイが直接彼女を助けてやるほうがより効果的だと言われたからだった。
これを機に、口うるさいエカティに恩を売っておくというのも悪くない。
ダイは暢気に自分に都合のいい未来図を想像しながら『黄金の夜明け学校』の門をくぐった。首に結ばれた五芒星の刺繍リボンが、正門をくぐる瞬間、微かに光る。
学校には必ず施されている魔法防御陣はダイの存在を拒まないのは、このリボンのおかげだった。
伝えられた場所までダイは駆け上がる。
まだ朝ぼらけの頼りない光の中、その小さな影は目当ての部屋を探り当てた。
室内は随分と使われた形跡がないわりに汚れや埃がなく、その片隅で小さく震えるエカティを見つけると、ダイは意気揚々と近づいて声をかけた。
「なにしょぼくれてんだ、そばかす女」
エカティは弾かれたように顔を上げる。正確には視線をさまよわせ、目の前でほくそえむダイの姿を見つけることに成功した。
「え? あんた、こんな場所でなにしてるの?」
「随分な言い様じゃねえか。折角おいらが恩をきせてやろうと思ってやってきたってのに」
「バカじゃない? どこの世界に恩をきせられて喜ぶヤツがいるって言うのよ」
「この場合、どんなにイヤだろうとそばかす女はおいらに感謝しなくちゃいけなくなるって寸法なんだ。どうだ、まいったか」
えへん、とふんぞり返るダイを尻目に、エカティは全身から力が抜けそうになる。
こんなくだらないことを言い合っている場合ではないはずだ。
「なら、さっさと助けなさいよ。まだ私のこと助けてもないくせに、威張ってるんじゃないわよ、このクソネズミ」
「おいらはクソネズミなんかじゃないやい。お前こそ助けられるのに威張ってるんじゃないぞ。少しはベスを見習ってみたらどうだ。そんなんじゃ、トリスに見捨てられても文句は言えないぞ」
ベスって誰だっけ、とエカティは思った。エカティはダイが結婚したことすら知らない。当然、エリザベスのことも知らない。だが、それよりもダイの台詞に聞き捨てならない箇所に噛み付いた。
「はあ? トリスが私を見捨てるわけがないでしょう? あんたがここにいるのだって、トリスに言われたからじゃないの?」
「ははん、おいらがなんでもトリスに報告してると思ってるんだろう。残念だったな。そばかす女を捜すようにトリスには頼まれたが、おいらがここに来たことはトリスは知らねえよ。こっそりお前を助けてトリスに褒めてもらうんだ。だから、黙って来たんだ」
本当の発案者は妻のエリザベスであるが、ダイは鼻を鳴らして自慢そうに言ってのけた。途端にエカティの頬がひきつる。
「あんたの小さな脳みそでくだらないこと考えてるんじゃないわよ。今は私のこと放っておいてもいいから、まずはトリスに報告してきなさいよ、このバカ」
「おいらに向かってバカとはなんだ。本当にこのまま帰っちまうぞ。いいのか?」
本心からエカティは帰ってもらいたかった。だが、徹夜でこの場所まで駆けつけたダイも簡単には引き下がらない。
「良いって言ってんでしょうが。どこまで頭悪いのよ。あんた一応、人語を解する魔族なんじゃなかったの?」
「もしかしなくても理解してるさ。そばかす女の言っていることだって聞こえてる。でも、おいらトリスの言うこと以外は聞かなくてもいいんだもんね」
エカティが動けないことをいいことに、ダイは尻尾でからかうようにエカティの頬を軽くはたく。
もう一声、心の底からわき上がる罵声を浴びせようとエカティが肩を震わせたときだ。背後の扉が開く音が聞こえた。
びくり、と全身が条件反射のように強張る。ダイは慌ててエカティの服のポケットにもぐりこんだ。
「起きてた? なにか声がしたような気がしたんだけど」
「……そうね。トイレに行きたいから声出してたのよ。聞こえたならちょうど良いわ。行かせてよ」
「いいよ」
昨夜の少年が軽く指を鳴らすと、エカティの手足を縛っていた拘束具が解かれた。
「この部屋の奥にシャワー室とトイレがある。勝手に使っていていいよ。でも、その前にこれはもらっておこうかな」
手首をさすりながら上体を起こしたエカティに近づくと、彼はエカティの上着のポケットに手を伸ばし、中に潜んでいたダイの長い尻尾をつまみあげて引きずり出した。
「きみの役目はこれで終わり。あとは試験終了後までここで好きにしているといいよ」
「なにすんだ、放せ。放せってば」
盛んに抗議の声を上げていたダイは、少年の声を聞いて顔を上げた。
「お前。……ノット・ハウライト」
「よく覚えていたね、ぼくの名前」
エカティは全身の血が氷ってしまったのではないかと思うほど震え、声を出すことも出来ずにその場に蹲っていた。
マルクは春の暖かな日差しを満喫し、惰眠を貪っていた。
こんな天気の良い日はおとなしく授業など聞いていられない。
モン・スーを散歩に飛ばし、自分は屋上で四肢を伸ばして寝そべっていた。
青く澄み渡る空は、モン・スーの翼の色に似ている。
やわらかい陽気はうとうとと眠気を誘うが、熟睡というよりは仮眠にちかい浅い眠りにしかならない。
耳元で小さな羽音がした。
「モン・スー? もう戻ってきたのか? 随分早いじゃないか」
青い小鳥は召喚士の顔の上になにかを落とす。
最初はいたずらかと思って相手にしなかったマルクだが、何度も何度も同じことを繰り返すモン・スーに答えてようやく思いまぶたを開いて言った。
「なんだ? なにかいいもんでも拾ってきたのか?」
再度、マルクの顔に落とそうと構えていたモン・スーのくちばしにある白いものを引っ張り出し、マルクは眺めた。
一見、無造作に丸められたただのゴミかと思った。だが、モン・スーがしつこく促すので、その紙のような物を無造作にひらく。
そこに滲むのは赤い文字だった。『助けて』とだけ書かれてある。
マルクは慌てて体を起こして確認する。
自分の周囲に同じような白い紙がたくさん並べてあった。その一つをモン・スーが加えてマルクの手に落とす。
「これも見ろってか」
それも同じように赤い文字で『助けて』としか書かれていなかった。
周囲に落とされた白いゴミを手当たり次第にひらいてみる。
『助けて』『助けて』『助けて』『助けて』
同じ言葉がただ一つだけ書かれた紙をマルクは掴んで立ち上がった。
「案内しろ」
肩にとまった青い小鳥が小さく鳴く。そして、マルクを先導するように屋上より見える別棟に向かって飛び立った。
ただの悪戯とは思えない。その赤い文字は所々茶色に変色し、微かな鉄さびの臭いがした。誰かの血で書かれた文字であった。
泣き疲れて眠ってしまったエカティが目を覚ましたのは、引きこもったバスルームのなかでだった。
備え付けてあったトイレットペーパーはもうない。
助けを求めるため、全て使い切ってしまった。
あれから幾ら叫んでも、少年もダイも戻ってくることはなかった。
また、他の誰の気配も感じることがない。
窓の外に丸めたトイレットペーパーを投げていて気付いた。エカティがいる周辺は、なにか大きな力で覆われているようだ。ある程度の文章を書いた大きい紙は、地上へ落ちる前に燃え尽きてしまう。
本当に小石ほどに小さく丸めたものだけが、かろうじて地上へ届くとわかってから、エカティは必死でその大きさに纏めることに集中した。
あんなゴミみたいな大きさもの、誰も広げてみようなどとは思わないかもしれない。
それでも何もせずにはいられなかった。
ダイはトリスに伝えてこなかったと言っていた。他にこの場所を知る者がいないのなら、悠長に助けを待っている場合ではない。
これから、どうしたらいいんだろう。
外部への連絡手段が思いつかない。ただ、ここで祈るように待つしかない。
コツコツ、と窓のほうで音がした。
見ると窓枠に小さな青い小鳥が止まっている。
視線が合っても逃げ出さず、こちらをみて軽く首を傾げて見せた。
「あなた、人間に慣れているのね。私が怖くない?」
小鳥は答えるように、嘴でガラスを軽くならした。
エカティはゆっくりと立ち上がり、窓辺へと近寄る。エカティを見上げる大きい黒い瞳が数度瞬いて、小鳥は片足を上げて頭をかく。その足には小さなリボンが結ばれていた。緑の細い糸のようにも見えるが、よく見るとそれには見覚えのある印章が刻まれている。
五芒星、それは召喚獣の証だった。
ダイの首に巻かれてあるリボンは赤い。それは召喚士が『青銀の夜明け学校』の生徒である証だ。緑は確か『黄金の夜明け学校』の生徒を示すものだったはず。
気持ちよさそうに目を細め、プルプルと全身を震わせ、小鳥はあらためてエカティを見上げる。
「あなた、召喚獣なのね? 私の言っていること、わかる?」
小さな鳴き声がタイミングよく答える。
エカティはダイ以外の召喚獣を見たことがない。それでも、小鳥の反応は人語を理解しているのだとわかった。
「お願い。あなたの主人に伝えて。トリスが危ないって。ダイが強制送還されちゃうって。このままだと私、トリスにあわせる顔がなくなっちゃう。私がトリスのこと守ってあげるって約束したのに……」
あのとき、喪服をまとう彼はまだ『赤銅の夜明け学校』の生徒だった。
その前に彼の父親の葬儀で見せた顔とはまた違う、別人のような大人びた顔で彼はそこにいた。
最後の身内を亡くしたいま、身寄りのない彼はこれからどうするのだろう。
エカティは父に引かれた手をほどき、トリスの傍に立つ。
「トリス、どこにも行かないでね」
彼の袖を引いてエカティは言った。彼は弔問客に向けていた大人びた顔をエカティに向けた。それがひどく寂しい、とエカティは思った。
「泣かないで、エカティ」
トリスは微笑んでエカティに言った。
「ぼくの家はここだもの。どこにも行かないよ」
「本当?」
こみ上げてくる涙で彼の姿がぼやける。
父の葬儀ではあれほど泣いた彼が、祖母の葬儀では泣かない。
こんなにも悲しんでいるのに、彼は泣けないでいる。
彼の祖母はエカティも大好きだった。
優しくて暖かくて、彼女のつくるスコーンは最高だった。
彼女が亡くなってしまったことは確かに悲しい。それ以上に、トリスが遠くへ行ってしまうことはもっと哀しかった。
「こんどは私が守ってあげるからね。トリスのそばにずっといるから。絶対先に死んじゃったりしないから。だからどうか、私を置いて行ってしまわないで」
手の甲で落ちる涙をぬぐいつつ、エカティは懇願していた。
遠くに行ってしまう彼を、どうにかして引きとめておきたかった。
「うん。ここにいるよ」
言葉とは裏腹に、彼はしばらく戻ってこなかった。
屈託のない表情はどこかに落としてきたのか、心から笑うことも少なくなった。エカティの家で世話をするようになっても、その表情にはどこか陰りが残っていた。
以前のような彼に戻って欲しかった。そのためにはなんでもした。
けれど、彼が昔の笑顔を取り戻したのは、偶然であった小さな魔族が同じ家に住み着くようになってからだった。
だから、エカティはダイのことが嫌いだった。
それは自分がどんなに努力しても叶わなかったことをやってのけた、小さき者に対する八つ当たりだったのかもしれない。
でも、一つだけはっきりとわかることがある。
目障りなダイを魔界へ還したいと思っていた。でも、エカティは思っているだけで、実行しようとはしなかった。
ダイに傷つけられたと申告すれば、ダイはおそらく強制送還されただろう。小さな傷なら幾つも付けられた。でも、申告しようとは思わなかった。
それはきっとトリスにとって、ダイが必要なことを知っていたから。
けれど、彼は違う。本当に実行してしまうだろう。
ダイがいなくなれば、トリスはまた遠くへ行ってしまう。
今度こそ、手を伸ばすこともできないほど遠くへ。
目の前にいた小鳥は、小さく羽ばたいた。
「待って、お願い」
思わず叫んだエカティのいる窓の前で、小鳥は翼の先に風を作る。それをエカティのいる窓へと向かって投げつけた。
反射的にエカティは右腕で顔を庇う。
想像していた衝撃はなく、エカティがおそるおそる顔を上げると、小鳥の姿は消えていた。窓に手をかけ、外を見ると、窓の下に人影を見つけることができた。
その青年の肩に、先ほどの小鳥が止まっているのが見える。
「これ書いたの、きみ?」
彼の手に握られた小さな紙は、確かにエカティが祈りをこめて落とし続けた救助を願うための一縷の望みだった。
|
|