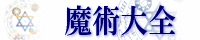 〜最下級召喚獣〜 3 〜最下級召喚獣〜 3 |
エカティ・エルバイトは自宅でイライラとしながら同居人であり幼馴染の、トリスティン・クロソライトを待っていた。
「少しは落ち着きなさい、エカティ。お前がイラついても事態は好転しないぞ」
父が娘を宥める声に「わかってるわ」と答えつつも、その態度に変化はない。
「だって、きっとまたあの迷惑ネズミのせいに決まっているわ」
先ほどトリス宛てに届いた封書は『青銀の夜明け学校』からのものだ。緊急事態でもないかぎりこの時期、個人宛てに学校から手紙など届くはずもない。
ダイを召喚した直後は、こういった手紙が頻繁にエルバイト家のトリスティン宛てに届いたものだ。学校からの手紙は、エカティの古い記憶を刺激せずにいられなかった。
「ただいま戻りました」
トリスの暢気な明るい声が響く。エカティは父の制止を聞きながら玄関まで駆け寄った。
「お帰りなさい、トリス。遅かったのね。あのね、今日は……あのネズミも一緒なの?」
「うん。マルクと『青銀の夜明け学校』のときの卒業認定試験について話し込んじゃったから遅くなったけど、今日はダイも一緒に講義受けに行ったんだ。ここにいるよ。でも、どうして?」
エカティがダイを気にすることは稀である。トリスに単純な疑問を抱かせる程度には不自然な行為だった。
「あのね、……その、学校から手紙がきてるの、トリス宛てに」
「なんだろうね」
首をかしげて考えるトリスに、エカティは自らの憶測を語ることは流石に躊躇った。
「居間で父さんが待ってるの。その、手紙のこと心配して」
「そうなの? じゃあもっと急いで帰ってくればよかった」
エカティと並び居間へ足を運ぶトリスの横顔は、特別動じている様子もなく、エカティの疑惑も少しずつ落ち着いてくる。
「おじさん、ただいま帰りました。手紙のこと、心配して待っていてくださったんですね。すいません、余計なご心配をおかけして」
「お帰り、トリス。手紙のことはそれほど心配していないんだが、エカティが落ち着かないようだったので一緒に待っていたんだよ。エカティは君を心配するあまり余計なことを口走りそうで、わたしはそっちのほうが心配だったんだ」
エルバイト家の当主はトリスの肩を叩くと、「わたしの力が必要なら遠慮なく言いなさい」とだけ言って自室へ向かっていった。
トリスは机の上に置かれた手紙を手に取った。
蜜蝋の印章は確かに『青銀の夜明け学校』のものだ。トリスは心配そうにこちらを見るエカティを落ち着かせるように笑って見せた後、封を開けた。
「あの、なんて書いてあったのか聞いてもいい?」
「明日、ダイを連れて学校に来いって書いてあるだけだよ」
「それって、前のときと同じなんじゃないの?」
エカティの言う前のときがなにを指すのか、トリスにもわかった。だが、それを即座に否定する。
「それはないよ。だって今日、ダイは殆どぼくと一緒にいたんだ。問題を起こす暇なんてなかったはずだよ」
「そう。それならいいんだけど……」
小さく呟くエカティに、トリスは笑う。
「本当に大丈夫だって。ダイが一緒にいたことは、マルクとモン・スーが保障してくれるよ」
エカティは拭い去れない不安を抱きつつも笑顔で頷いた。
そして、結果的にはエカティの不安は的中したのだった。
翌朝、ダイを連れて登校したトリスを待っていたのは審問会だった。
昨夜、召喚獣講義を受けていた『黄金の夜明け学校』の魔法実験準備室が荒らされたのだという。それはまるで、ダイが召喚された直後に引き起こした悪戯に酷似しており、事情を聞きたいというものだった。
「では、身に覚えがないというのですね。トリスティン・クロソライト」
「はい。昨夜の私および我が召喚獣の身の証は、同じ若年召喚獣講義をうけている『黄金の夜明け学校』二年のマクル・カイアストライトおよび、彼の召喚獣モン・スーにお尋ねください。答えてくれるものと思います」
居並ぶ達人レベルの魔術師たちを前に、トリスは平静で答える。この二年間、ダイの悪戯の後始末で培った経験だ。
感情的になってはいけない。淡々と事実だけを述べる。それが最短の解決方法であることを学んでいた。
「その『黄金の夜明け学校』では、貴方とその召喚獣に直に話を伺いたいと言ってきていますが、どうしますか?」
「いつでもお引き受けいたします」
ダイはトリスの手の上で、ちんまりと座って口を開かないでいる。
こうした場で、己が迂闊に発言することはトリスの足を引っ張ることでしかないことを、この小さい召喚獣も身にしみて理解していたのだ。
「荒らされた実験準備室には爪跡や歯型が残っているそうです。おそらく貴方の召喚獣のものと照合を求められると思いますが、それでも良いのですね?」
「はい。構いません」
「そうですか。では、こちらもそのように伝えることにいたしましょう。貴方の言い分も先方には伝えておきます。マルクという生徒に話を聞く時間も必要でしょう。貴方は卒業認定試験も近いことです。今日はこのまま通常の授業にお戻りなさい。先方への事情説明も、その点を考慮してくれるように伝えておきます」
中央に座る大達人、マグレガー・メイザースは手元にある書類になにかを書き込むと、トリスに退出を促した。
「わかりました。失礼いたします」
一例をし、トリスはダイを連れて審問室を出る。
途端にダイがそわそわと落ち着きをなくす。
「な、トリス。なんでおいらが疑われているんだ? 爪跡や歯型があればおいらのせいなのか? おいら、魔界に強制送還されちまうのかな」
尻尾の先が落ち着きなくゆれる。トリスはダイを肩に乗せ、笑った。
「大丈夫だよ。だって、ダイは昨日、ずっとぼくと一緒にいたじゃないか。マルクやモン・スーは証言してくれるよ。それに、審問室って嘘をついたら即座にわかるよう、見えない魔法陣がしかれているって聞くよ。なにも反応しなかったじゃないか。昔のこと、忘れたの?」
「覚えてるよ。覚えてるんだけど……」
最初の悪戯を仕出かした頃、ダイは散々デタラメを言い張り、光り輝く法陣が何度も審問室に浮かび上がったものだ。
だが、ダイは不安そうに尻尾をぱたぱたとせわしなく動かしていた。
「昨日からダイ、変だよね。ノットのこと避けるし、変なこと心配するし、らしくないよ」
「昨日のあれは、なんとなく、嫌な感じがしたんだよ。あの召喚士、絶対に目が笑ってなかった。そりゃ、火蜥蜴はおいらより上位だけど、上位魔族が怖いなんてこと言ってたらおいらは外に出られなくなる。絶対にあいつは敵意持ってるんだって。おいらよりもトリスが狙われてるんじゃないのか?」
「ぼくが? なんでさ。ぼく、ノットになにもしてないよ。会って二回目だしさ」
「ふーん、でも、悪意の理由なんて、逆恨みでも十分だろう。とにかく、あいつには気をつけろよ。おいら、敵意や悪意には敏感だって自信があるんだ」
髭を震わせて盛んに主張するダイに、トリスは「はい、はい」と適当な返答をする。
「トリス、おいらの言ってること、信じてないだろ?」
「そんなことないよ。でもね、何もされていないうちから身構えても始まらないでしょう? それだけ」
「暢気すぎるぞ。もっと気をつけてかかれ」
「わかったよ。心配性なんだから」
この事件に関しては、マルクとモン・スーの証言から無罪放免になった二人だが、本当の問題はここから始まっていた。
それからも小さな事件が頻発した。
いずれも、現場には小さな爪跡と歯型が残され、そのたびにトリスとダイは審問会に呼び出しを受けた。
最初のうちは証人もいたが、そのうち、どうやっても潔白を証明できない時間にも事件が起こり始めた。
そのたびにダイの爪、歯型を提出しては弁明するということの繰り返しになってくる。疑わしきは罰せずを信条としている学校であっても、その噂は広がる。ましてや前科がたっぷりある召喚獣である。
徐々にだが、ダイへ向けられる視線は冷たさを増し、トリスにも同様の視線が向けられる。
さっさと送還してしまえ、と言葉にされないまでも周囲の雰囲気は明らかにそれを求めていた。
「ダイ、ぼくの家の屋根裏にいたほうが良いんじゃないの?」
あからさまな拒絶の視線が多くなってきたころ、トリスはダイにそう提案した。だが、ダイは譲らなかった。
「だって、おいらなにもしてないぞ。何度も爪や歯の型だって提出したし、審問会だってそれを認めてくれてるのに、おいらが隠れたら噂が本当だって言っているみたいだぞ。そんなの絶対イヤだ。それに、おいらはトリスが信じてくれてたらそれでいいんだ」
「無理はしないでね」
温室が根こそぎ荒らされた。標本の稀少鉱物がかじられた。こんなことはまだ可愛いものだ。
生徒の提出プリントが教室中にばらまかれていたり、魔術成績のふるわない者の答案だけをわざと『落第決定』と書いて掲示板に張り出したり、教科書を全て紙くずにされた生徒も出てきた。
卒業認定が間近で神経質になりがちな生徒のなかで、これは結構衝撃的な出来事だった。
クラスメイトの半数以上はトリスを避けるようになり、一部の噂に惑わされない人間だけが普通に話をしてくれる。エカティやロゼットもその一部の人間だった。
「これだけ注目されていたら、証人みつけるのにも困らないよね」
トリスは一人ごちる。だが、その言葉を拾ったロゼットははっきりと言い切った。
「そうよ。だからこそ、誰にも文句を言わさない状況を作り上げることが大切なの。煩わしくても少しの間は我慢するのね」
教室内どころか、校内にいるだけで視線が常につきまとう。それがわずらわしくもあり、反対におかしくもあった。それでも、いつものように屋上でランチを取らないのは、ロゼットの提案を受け入れたからだ。
衆人環視のなか、トリスとダイが別の場所で姿を見られている間に他所で事件が起これば、誰もダイを疑うことなどできない。
「うん、わかってる。でも、エカティがダイを信用してくれるとは思わなかったよ」
ダイとは犬猿の仲とも言えるエカティは、少し頬を膨らませて抗議する。
「だって、目の前にこのネズミがいるときに事件が起きたんだもの。疑うわけにいかないじゃない」
片手を超える事件が起こった頃だろうか。担任教師に呼び出しを受けたトリスは、ダイを連れて指定された場所に向かった。だが、担任教師はそこにはおらず、掃除当番だったエカティとはちあわせしたのだ。
結局、教師はトリスを呼び出した覚えはないというし、同じくダイとケンカをしながら教師を待っていたエカティがいたおかげで、その日、法具室を滅茶苦茶にしたのはダイではないという結論に達したのだ。
随分と貴重な法具が粉々にされていたという。
エカティは大きくため息をつく。
「本当に一生の不覚だわ。あれさえなければ純粋に疑っていられたっていうのに」
「そばかす女は単純だからな。嫌いなヤツは悪いヤツって図式しか頭にないんだろう」
「ダイ、そういう言い方は良くないよ。あのときはエカティに助けてもらったんだからね」
「頼んでないもん」
「頼んでなくても結果的に助けてもらったんだから、文句言わない」
同じ机の片隅で、トリスにもらったりんごにかぶりつきながらダイはふてくされる。
「ごめんね、エカティ。ダイも本当は感謝してるんだよ。上手くお礼がいえないだけなんだ。許してやって」
「そんなことは慣れてるし、どうでもいいんだけど、トリス、こんなことされる心当たり、本当にないの? このネズミはありすぎてわからなさそうだしね」
恨みをかっているのなら、エリザベスをめぐる男の戦いはたくさんあったそうだが、エリザベスに求婚していたほかのネズミは多すぎて、絞り込むことが困難だとダイは言う。
『青銀の夜明け学校』は魔法防御が施されているが、それは魔力を持つものにしか有効ではないという。だから、ダイの恋敵が逆恨みをしたという可能性は多分にある。でも、これほど続くものだろうか。
「多分、普通のネズミは関係ないわ。それほど知恵もないだろうし、こんな手の込んだことできないから」
ロゼットは断言する。こういうとき、抜群の記憶力と知識と洞察力を持つ彼女が見方であることは有り難い話だった。
「手の込んだことって、作為的な事件ってこと?」
「そう考えたほうが自然だわ。現場に残されるのは決まって爪跡に歯型。私が本格的にトリスの鉄鼠を犯人に仕立てたいのなら、その体毛も残すけれど、きっとそれは入手できないでいるか、残せない事情があるんだと思うわ。でも、きっとその鉄鼠を直に見たことはあるはずよ。歯の大きさ、爪の長さはおおよそで似通っているんでしょう?」
「うん、審問会でもそう言われたよ。でも、ちゃんと鑑定すると違っているって言われたんだ」
「でも、このネズミは召喚直後から結構自由に動き回っていたから、見たことある人は多いんじゃないかしら」
エカティは首をひねる。
「遠目にならね。でも、目測で大きさを測定できる範囲となれば別。知ってた? この学校でトリスの鉄鼠にそんな至近距離まで近づけるの、エカティくらいだったのよ」
「え? 私は違うわよ」
「それもわかってる。そんな手の込んだこと、エカティはしないもの。いつもみたいに正面から怒鳴りあうほうが先よね。ねえ、トリス。最近新しい若年召喚士が増えたって聞いたけれど、その子はどういう感じの子なの?」
いきなりロゼットから話をふられ、トリスは少し考えながら答える。
「どうって、普通の子だよ。でも、彼の召喚獣は爪も歯もない火蜥蜴なんだよね。関係ないんじゃないかな」
「確かに、火蜥蜴には鉄爪や型を残せるほどの強靭な歯はないけれどね」
ロゼットが考える素振りを見せると、ダイが大きく主張した。
「そいつイヤなヤツだぞ。トリスにも気をつけろって言ったのに、聞かねーんだもん」
「イヤなヤツって、どんな風に?」
「知るかよ。とにかくこう、目だけ笑わない感じのイヤなヤツだ。ノット・ハウライトってのは」
「ノット・ハウライト?」
ロゼットは急に視線をあげてダイを見つめる。ダイは慌ててトリスに確認した。
「ああ、ヤツはそう名乗ってたぞ、な、トリス」
「うん。そうだけど、ロゼット?」
問いかけるトリスの言葉はロゼットの頭上をすり抜けていく。彼女は既に広げたランチの存在も忘れたかのように何かを考え込んでいた。
「ハウライト家ね。ふーん」
彼女の脳内だけで、なにかが組み立てられているのをエカティは感じていたが、何も言わなかった。
確証を得られるまで何も語らない。集中すると周囲の存在を無視してしまう。ロゼットはそういう点で大層誤解されやすいのだ。
薄暗くなる図書室で、ロゼットは両脇に高く積み上げた書物の間に埋もれていた。
「あった、これだわ」
その法陣を見て、ロゼットは溜息をつく。
記憶違いであれば良いと思っていた。でも、自らの記憶に自信があるからこそ、目を背けるようなまねだけは出来ない。
迷いはある。
これを告げたら、彼らの瞳に不信がともるかもしれない。離れていくかもしれない。
自分がここにいる理由の一端でもある過去の事件を知られてしまうかもしれない。
他人から受ける軽蔑も侮蔑も嘲笑も哀れみも、全部慣れたと思っていた。けれど、自らそれを選択することは苦しい。
組んだ両手を額にあてた。
黙っていることは彼らを更に苦しめるだろう。
苦い思いをかみ締めるように決意し、顔を上げたロゼットの前に、意外が人物が立っていた。
「あなた、どうしてここに?」
「それはこっちのセリフだよ。ベリル博士のお嬢さん。最初は見間違いかと思ったけれど、まさか、こんな地方にいるなんて思わなかった」
そう、彼はかつての自分を知っている。
その名を聞いたとき、嫌な予感はした。そして、それは的中した。
「『白金の夜明け学校』創始随一と言われた天才少女が、こんな田舎の『青銀の夜明け学校』にいるなんて思いもしないよね。それとも、これってなにかの冗談?」
「あいにくと、冗談じゃないわ」
「じゃあ、クロソライトの傍にいるのも必然ってわけじゃないんだ」
「偶然よ。知っていたらここに来なかったわ」
「そうだよね。一度は完全に敵対した家同士だものね」
口にしたくない過去を、彼は知っている。隠しておきたいと思っていた。知られずに済めばいい。けれど、この願いはもう叶わないだろうとも悟っていた。
彼が黙っているはずがない。
「とりあえずさ、静観していてくれたら黙っておくけど? だって、あいつら全然知らなさそうだもん」
ロゼットをうかがう彼の表情は愉悦の色にあふれている。
いたぶられるだけの弱い立場にあるロゼットは、是とも否とも答えずにただこぶしを握り締めた。
「邪魔もしないでよね。じゃないと今の日常が壊れちゃうよ?」
小さく笑いながら去っていく彼を見送り、ロゼットは唇をかみ締めた。
もっと早く言えばよかった。
誰かに脅されるくらいなら、先に自分で告げたほうがずっと良かった。
けれど、全てを捨ててしまえない自分がいる。
これは彼らを裏切ることになるのだろうか。
逃げられない過去と捨てられない現実の狭間でロゼットは迷っていた。
数日後、事件は思わぬ方向に流れた。
『青銀の夜明け学校』の生徒が校内で襲われたのだ。
背中に深い三本爪の跡が残っていたという。発見が早かったので命には別状なしとのことだったが、その疑惑は渦中の人物とその召喚獣に向けられた。
「変な目で見ないでよ。トリスがそんなこと許すわけないでしょう」
エカティが鋭い視線を向けると、周囲は視線を逸らした。
先日まで一緒にランチを囲んでいたロゼット・ベリルが当の被害者だった。
「大丈夫なのかな」
「ロゼットの意識が戻ったら、トリス達の疑いを晴らしてくれるわよ。それまでの辛抱だからね」
「わかってるよ。でも、エカティも念のためにぼくから離れたほうがいい」
微笑むトリスの横顔には、疲れのようなものが見え隠れしていた。
「冗談じゃないわよ。私は離れないんだから」
「離れていろよ、そばかす女。頭悪いな」
「うるさいわね、ネズミは黙っていなさい。でも、第三者の証言が必要になるときだってあるでしょう?」
最初の部分はダイに、後半はトリスに向けた言葉だ。だが、トリスは首を横に振る。
「これだけ監視されるほど注目浴びているんだから、それは大丈夫。それに、卒業認定試験の準備だってあるだろう?」
それはトリスも同じである。だが、召喚獣持ちのトリスは、形ばかりの認定試験になる予定だった。エカティとは勉強範囲もまるで違う。
「ぼくらは大丈夫。ちゃんと人目がある場所に居るようにする。だから心配しないで」
トリスは笑う。だが、エカティはやんわりと突き放された気がしていた。
審問会への招待状が家に届くのは時間の問題だろう。
三本爪は鉄鼠の特徴でもある。
「ダイ、今度はこっちから出向いていこうか。待っているだけなんてつまらないよね」
「ああ、それいいな」
彼らは急いで校内の一室へ向かった。いつも審問会が行われる部屋の扉を叩く。これだけ事件がおき、まして傷害事件までおきたいま、審問会のメンバーが集っていないはずがない。その想像は現実のものとして彼らを迎え入れた。
「どうしました。トリスティン・クロソライト」
「ロゼット・ベリルの件についてお伺いにきました。どうせ、呼ばれることになると思いましたので、こちらから出向きました。ご迷惑だったでしょうか?」
達人クラスの魔術師は顔を見合わせて苦笑する。
まあ、何度も呼び出した過去の事例ならともかく、傷害事件ともなれば保護者同伴になる。彼の身内は死に別れて久しい。少年の判断はある意味的確で、その聡明さが今の庇護者を慮っていることも察せられた。
「良いでしょう。彼女の背に三本爪の跡があったという話は広がっているのです。今更貴方達に隠したところで疑惑の渦中から逃れることなど出来はしないでしょう」
「では、彼女を襲ったのは鉄鼠という結論は覆らないのですね?」
「ええ。我等はそう判断しました。そして、現在認知されている鉄鼠は貴方の召喚獣のみなのです」
審問会代表でもある大達人マグレガー・メイザースは静かにそう告げた。
これまでの悪戯と片付けられる程度の問題ではない。それはトリスにも理解できた。
「そこで提案があるのです。次の事件が起きるなどという想定をすること自体、ゆゆしき問題ではありますが、貴方の召喚獣鉄鼠をしばらく拘束することを容認してもらえるでしょうか」
「イヤだぞ。おいらなんにもしてないんだ。拘束なんて冗談じゃない」
少年の肩で鉄鼠が全身の毛を逆立てて怒っていた。
「ええ、ダイオプティース。おそらく貴方の言葉に嘘はない。ここにいる全員はそれを認めます。それでも時として、世間に認めさせるためのパフォーマンスは必要だとも考えているのです。返答はもちろん猶予を与えます。貴方達で相談して決めてきてください」
それは審問会という厳しい場に揃う達人のぎりぎりの譲歩なのだろう。
トリスは「考えてから数日後に返答します」と言うと一礼して審問会の部屋を退出した。
エカティは落ち着かない様子で教室の中を行ったりきたりしていた。
友人のロゼットが怪我で入院、幼馴染のトリスがその原因と噂され、落ち着けというほうが無理な状況である。
審問会の存在は知っていたが、エカティの人生でその存在には縁がなかった。つまり、問題となる行動をとったことがなかったのだ。
『○○の夜明け学校』と名のつく魔術師養成学校は、三人の創立者がいる。
ウィリアム・ウィン・ウェストコット
マグレガー・メイザース
ウィリアム・ロバート・ウッドマン
この学校に入学して最初に覚える名前である。現存するのはマグレガー・メイザースただ一人。彼は審問会の代表として、各『夜明け学校』の学長として、そして大達人の称号を持つ魔術師として有名である。事実上の最高指導者だ。
私なんかが訪ねても、会ってくれないかもしれない。
エカティは思う。
トリスのように秀でた才能はない。ロゼットのように優れた頭脳もない。平凡な一生徒でしかない自分が直談判の相手として不足していることを自覚していた。
それでもなにかしたい。自分に出来ることはないだろうか。
「エカティ、あなたにお客さん。門のところで待ってるって」
クラスメイトの女の子がエカティに声をかけてきた。
「誰?」
「さあ、見かけない顔の男の子だったよ。ここじゃないけれど、同じ『青銀の夜明け学校』の生徒だって言ってた。結構ハンサムだったよ、彼氏? 浮気してるとトリスに言いつけちゃおうかな」
「違うわよ。もう、変なこと言わないで」
顔を赤くして否定するエカティに、「ごめん、ごめん」と謝ると、今度は少し真面目な顔で続ける。
「トリスのことで心配して来たんだって。様子を知りたいって言ってたよ」
「もう、そういうことは早く言ってよ」
慌てて教室を飛び出したエカティは、そのまま行方不明になった。
その夜、エルバイト家のなかは重苦しい雰囲気に包まれていた。一人娘が行方不明になっているのだから明るくなるはずもない。
「トリス、なにか知らないか?」
「いいえ。ぼくが席をはずしている間のことだったので、詳しくはなにも。でも、エカティと比較的仲のよい子が、誰かに呼び出されていたと教えてくれました。今、ダイが町中のネズミを総動員してエカティを探してくれています」
「そうか。君たちにも迷惑をかけてしまったな。すまない」
白髪交じりの頭を下げるエルバイト家の当主を前に、トリスは本当のことを言えずにいた。
「お願いだから謝らないでください、おじさん」
全てを話すとなれば、トリスとダイが色々と疑われていることから話さなければならない。そして、エカティがそれに巻き込まれたらしいことも必然的にわかるだろう。
エルバイト家の当主は、事情を知ったところで決してトリス達を責めたりはしない。それがわかっているから、なんとかして自分たちだけで解決したいと思っていた。
こういう事態が起これば、ダイを拘束などしていられない。
ネズミというのは縄張り意識が強く、連帯行動など取らないと思われているが、その裏でネズミ網という情報網があるのだとダイは言う。
人間が仕掛けた新しいネズミ捕りの罠であったり、ばら撒かれた毒薬であったり、最初のうちは斬新な手法で捕らえられることがあっても、ネズミ網でその知らせは巡るそうだ。
「おいら、ちょっくら行って、あのそばかす女を探してもらってくる」
ダイはそういうと、騒ぎが大きくなり始めた教室からこっそりと出て行った。
本当ならこの時期、ダイの単独行動は避けるべきだっただろう。それでもトリスは許した。いま優先させるべきは巻き込まれたエカティの安否であって、自分達の保身ではないと思っていたからだ。
一方で、ダイはトリスの願い通り、ネズミ網にエカティの捜索を依頼したものの、すぐにトリスのもとに戻るのではなく、エリザベスの顔を見に新居へ足を向けていた。
もともと、トリスはダイを自由に行動させていた。最近の疑惑さえなければ、ダイは楽しい新婚生活の真っ最中だったのだ。
慣れない我慢をしていた生活の息抜きに、ダイは意気揚々と新妻のもとへ帰る。
「たっだいま〜、ベス。悪いな、一人ぼっちにさせちまって。寂しかったろう?」
白いハツカネズミは小さく鳴いて夫を迎え入れた。
「仕事だったんだよ。トリスが困ってるんだ。おいらが助けるのは当然だろう。本当はそばかす女のことなんてどうでもいいんだけど、トリスが気にしているからな。おいら、自分で言うのもなんだけど、いい召喚獣だと思わねえ? え? もう見つかったって知らせが来たのか。いつ?」
妻の答えを聞いて、ダイは困ったように髭をなでた。
「そうか。面倒くさいな。それならトリスに教えるのは明日でもいいかな。え? ダメ? うん、わかったよ。行ってくる……違う? ……ああ、そうか。そっちのほうが早いかな。ベスは賢いな。うん、わかった。さっさと行ってくるよ。今夜中には戻ってくるから待っててくれよな」
久々に会った妻は、ダイの仕事に理解があるのか、家主であるトリスに気を使ってか、すぐにダイを送り出す。
ダイは、知らせを受けたことをトリスに伝える前に、妻の提案にのることを優先した。
そうすることがトリスのためになると信じて疑いもしなかったのだ。
|
|