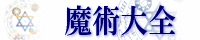 〜最下級召喚獣〜 2 〜最下級召喚獣〜 2 |
この『青銀の夜明け学校』という学校は一風変わっている。
『光あるもの(ニオファイト)』と呼ばれる異能者が、その特殊能力を伸ばすためだけに存在するような学校だ。ただ、その能力は生涯保障されているものではない。半数くらいの学生は幼くしてその能力が自然消滅してしまうことが多い。そのため、一般の学校にも適応できるように普通のカリキュラムも組まれている。
入学許可された子供は『赤銅の夜明け学校』と呼ばれる学校に六年間通う。そこで能力を失うか、与えられた課題をマスターできないほどの微弱な力しか持ちえないと判断された者は、その上にある『青銀の夜明け学校』に進むことができない。その『青銀の夜明け学校』は三年間就学の後、更に上位にある『黄金の夜明け学校』に進学できるかどうかが決まる。最高学府は『白金の夜明け学校』と呼ばれ、ここを卒業できたなら『小達人』という称号を得られる。これがあれば、この世界ではなんとかその道で生活できるレベルということになる。
一つの課題をクリアするのに、おおよそ三年の日程が組まれている。
『赤銅の夜明け学校』での前半に地属性を学び、後半で風属性を身につける。『青銀の夜明け学校』で水属性を、その上の『黄金の夜明け学校』で火属性、ここまでで一通りを『魔術技術(ウィッカクラフト)』の基礎をマスターしたという認定はもらえる。だが、『魔術師(ウィザード)』を正式に名乗りたければ最終課程の『白金の夜明け学校』を卒業できなければその肩書きを口にすることは許されない。
入学当初から『魔術師』を名乗るまでの過程で大半が脱落、もしくは能力を失ってしまうのが現状だ。
トリスは代々魔術師を名乗ってきた家柄だった。
数年前に仕事中に死亡した父も、一昨年老衰で亡くなった祖母も、魔術師であり、召喚士であった。幼いころに亡くなった母は普通の人間だったと聞くが、トリスにとって記憶のすみにある母の姿は微笑を絶やさないおだやかな女性だった。彼にはそれで十分だった。
トリスティンとエカティの家族とは家が隣同士で両親の生前から仲が良かった。
父とよく組んで仕事をしていたというエカティの父は、一昨年、最後の身寄りを亡くしたトリスの世話を引き受けてくれていた。家の中にトリス専用の部屋を与え、食事の世話から身の回りのことまで気を遣ってくれる。トリスが相続した財産には手をつけず、一人前になるまでは遠慮するな、と言ってくれている。
ありがたいことだ、とトリスは思っていた。けれど、エカティの家にいると時々むしょうに苦しくなる。寂しいとか孤独だとか思ったことはない。とても親切にしてもらっている。気にかけてもらっている。だから、こんなふうに思うのは贅沢なのだと自分に言い聞かせていた。
今日もエカティの母に持たせてもらったお弁当を広げ、トリスは肩に乗せたダイの話に耳を傾けていた。
「ベスはな、あ、彼女はエリザベスっていう名前の白いハツカネズミなんだけど、彼女は家族でパン屋の屋根裏に住んでるんだ。ベスのことは結構有名でさ、最初はすっごい美人だって噂を聞いて見に行っただけだったんだ。ほら、噂ってあてにならないじゃん。けど、実際見に行ったらすっごい美人でさ、おいら、こんな彼女だったら魔族じゃなくても嫁さんに良いなって思ったんだよ。普通のネズミは魔族なんて見たことないじゃんか。彼女もおいらが魔族だって言っても全然信じてくれなくてさ、苦労したんだよ。だっておいら、特に術が使えるとかないし、魔族の特徴があるって姿じゃないじゃん。人語喋るって言って見せても、ベスには理解できなくてさ、でも、このリボン見せたらころっと変わるんだぜ」
トリスのお弁当からちょいと失敬したりんごで頬袋をいっぱいに膨らませ、ダイは機嫌よく語っていた。
「あ、変わったのはベスじゃなくて、ベスの両親だったんだけど、それまで胡散臭い縄張りあらしとか思われていたみたいだったのに、このマークは本物だって大騒ぎさ。それで、ベスもおいらが本当に魔族だって信じてくれたんだ。ベスにはそれこそ行列ができるほどの求婚者がいて、でも魔族のおいらのほうがいざというとき娘を守れるに違いないっていうんで、おいらの嫁さんにくれるってことになったのさ。それでもさ、肝心のベスにその気じゃないとダメじゃんか。だからおいら、最近ずっと毎晩通ってベスに求婚してたんだよ。最初は親が決めた相手なんてって、ちっとも話を聞いてもらえなかったんだけど、毎日ベスの好物だっていうチーズを持っていったからなのかな、さっきやっとベス自身がおいらと結婚してもいいって言ってくれたんだ」
「そう、良かったね。ダイはそのエリザベスさんをお嫁さんに決めたんだ」
「うん。でも、ベスは魔界には連れて行けないんだよ。魔界は魔族じゃないと多分住めないくらい環境が悪いから。おいらの両親に紹介できないのは残念だけど、いつかきっとベスのことみたら両親も許してくれるって思うんだ」
「そうか、おめでとう、ダイ。いつかぼくにもエリザベスさん、紹介してよね」
「おう、当たり前だ。トリスには一番初めに紹介するぞ。今晩にでも連れて来たいんだけど、今夜はそばかす女の家にいる日だよな。ベスを連れて行くのは無理だよな」
「週末、ぼくの家で過ごす日に連れておいでよ。あそこなら大丈夫だよ」
「わかった。でも、ベスがいくら美人でも、トリスには譲らないからな。それだけは覚えておいてくれよ」
「うん、ダイの大事な相手に横恋慕するほど野暮じゃないつもりだけど、信用ないかな、ぼく」
「そんなことないぞ。ただ、一応言っておかないと、あとから言われてもおいら困っちまうからな」
慌てて首を振るダイを見て、トリスは笑う。
そもそも人間のトリスにネズミの美醜はわからない。全くの取り越し苦労であるが、ダイはそんな単純なことにも気付かない。よほどネズミ基準では美人なのだろう、とトリスは思う。
「結婚祝いはりんごとチーズでいいぞ。おいらはりんご好きだけど、ベスはチーズのほうが好物なんだ。パン屋で生まれ育った都会のネズミってのは、好物も洒落てるもんだよな」
当然の顔で結婚祝いを要求するダイに、トリスは笑う。
「そのくらいならお安い御用だけど、ダイ、毎日通っていたときに持参したチーズって、エカティの家から盗んでいったりしてないよね?」
想像外の言葉だったのだろう。一瞬だけちらりとトリスを見上げると、ダイはそっぽを向いて答える。
「そ、そんなことないぞ。だいたいはベスの家のパン屋から運んだんだ」
尻尾の先が不安そうに揺れる。言葉と裏腹にその尻尾の先が真実を雄弁に語っていた。
「だいたい、ね」
「そう、だいたい……」
帰ったら世話になっているエルバイト家のおばさんに謝らないと、とトリスは思いつつ、ダイを責めることはしなかった。
ほぼ同時刻、エカティ・エルバイトは教室でトリスティン・クロソライトと同じ中身のお弁当を広げ、友人とランチを楽しんでいた。
ダイに付けられた鼻頭の傷は、トリスとダイが姿を消してからすぐに治した。
エルバイト家は治癒術では名の知れた家系である。エカティもどの教科より治癒術が得意だった。
「それにしても、あのネズミは目障りだわ。トリスの足引っ張ってばっかり。どうにかして魔界に還せないものかしら」
彼女の家にトリス世話になっていることは誰もが知っていることだ。そして、エカティとダイの相性が悪いこともよく知られていた。幼馴染であり、現在は同じ家に暮らす彼女がトリスを誰よりも気にかけている。
「そうは言っても、召喚獣を戻す権限は召喚士にしかないからね。先生方も随分トリスを説得なさったそうじゃない。でも、トリスが絶対に頷かないんでしょう?」
ロゼットは毎日のように聞かされるエカティの愚痴に、お決まりの台詞で返す。
言っても仕方のないことなら、考えるほうが無駄というものだ、と彼女は思っていたが、エカティはそう思わないのだから仕方がない。
「そうなのよ。それが一番解せないわ。あの役立たずのなにが気に入っているのかしらね、トリスは」
「それは本人に聞いてみないとわからないわよ。こんな所で想像していたって仕方のないことばかりじゃない。それにエカティは、そろそろトリス離れしたほうがいいわよ」
「トリス離れって、人聞き悪いこと言わないでよ。別にトリスに引っ付いているわけじゃないんだから。ただ、幼馴染だし、トリスはお身内がいないわけだし、うちでお世話しているんだから、やっぱり気になるでしょう?」
「そうかしら。エカティは全般的に誰に対しても面倒見がいいと思うけれど、トリスのことになると目の色変えているように思うわよ。それにね、トリスに近づきたいなって思っている女の子がいたとしたら、エカティの存在ってすごく気になってしまうと思うのよ」
思わぬ友人の言葉に、エカティは驚いた。
「えっ? そんな女の子がいるの?」
「たとえばの話よ」
ロゼットは意味ありげに笑い、エカティの慌てた顔を見てこっそりほくそ笑む。
学年一の秀才であるロゼット・ベリルの名は、珍しく若年で召喚獣を持つトリスと同様に有名である。彼女の才能は桁外れの知識と記憶力だ。一度見たものは忘れない。うらやましいと言われがちだが、ロゼット自身は気にするふうでもない。
ただ、昔から周囲に一目置かれるということが当たり前になりすぎて、普通の友人をいう存在には縁遠かった。そう、エカティに出会うまでは。
「エカティは気がついていないんでしょうけれど、トリスって普通に考えれば将来有望出世株なのよね。召喚獣持ちってことは少なくとも『黄金の夜明け学校』の卒業資格まで保証されているわけだし、彼の召喚術を考えればその上だって十分ありえるでしょう? 見た目だって悪くないし、基本的に優しいわよね。うるさい親はいない、財産持ちだし家もある。家系的にもそこそこ名が知られているでしょ? ただ、本人が目立つことを避けているから地味に思えるだけで、あと数年も経てば、彼みたいなタイプはモテると思うわ」
「……からかってるんでしょう? ロゼット」
恨めしそうに自分を見るエカティに、ロゼットは肩をすくめる。
「半分はね」
「半分? だったら、残りの半分は?」
「客観的考察による推理と分析の結果よ。私、エカティをからかうのは好きだけれど、デタラメを言って惑わすほど子供じゃないわ。今は卒業認定試験に集中するべきときなんでしょうけれど、ちゃんと進学できたなら、もう少しお互いの関係を考えてみる時期に来ているんじゃないかしら」
「でも、そんな考えるような関係じゃないもの、私たち。小さい頃からっていうか、生まれたときから……ううん、生まれる前から知り合いみたいなもんなのよ。母さんのお腹にいるときから、トリスのお母さんとうちの母さんは良くお喋りしていたって聞いたもの。姉弟みたいなもんなの」
「ふーん。だと良いけどね」
懸命に言い訳を並べるエカティを他所に、ロゼットは自分の昼食を食べることに専念していた。
月に一度、トリスは『黄金の夜明け学校』の門をくぐる。
若年のうちから召喚獣を持つものに義務付けられている講義を受けるためだ。
現在、トリスのほかにも召喚獣を持つ規定年齢以下の者がいる。
マクル・カイアストライト。彼は『黄金の夜明け学校』二年の生徒だ。一昨年まではトリスとは違う『青銀の夜明け学校』に所属していた。この講義がなければ知り合うこともなかった二人だが、トリスとマクルは年齢の違いを超えてそれなりに気があっていた。
「よっ、トリス。久しぶり」
教室の扉をあけると、マクルが手を上げてトリスを呼ぶ。
「マクル、久しぶり。モン・スーも元気そうでなによりだね」
トリスはマクルの腕に止まり、小首をかしげる鳥にも声をかける。小さな青い鳥はそう見えない可愛らしい外見ではあるが、れっきとした魔族である。
隣に腰を下ろすトリスをみて、マルクは尋ねる。
「ダイは? 今日も連れてきてないのか?」
「うん。お嫁さんもらったから、しばらくは新居探したりするのに忙しいんだって。今日も夜に帰るって言ってたよ」
「嫁? 相変わらず自由気ままに行動する召喚獣だな。トリスはそれで平気なのか?」
「うん、まあね。閉じ込めていたって仕方ないし、ダイはダイでしたいこともあるだろうから」
「だから、お前はダイの後始末に謝罪してまわるんだな」
「もう慣れっこなんだよね」
「そういうの、慣れちゃまずいだろ」
「やっぱりそう思う?」
「思うさ。でも確かに、ダイならカゴに閉じ込めたところで脱走するのがオチなんだろうな」
トリスの召喚獣を思い出し、マルクは呟く。
口達者で行動的、と言えば聞こえが良いだろう。だが、実際のところ、ダイはトリス以外には基本的に冷たく、憎まれ口しか叩かない。マルクに対しても、モン・スーという召喚獣がいるからトリスの仲間という認識はあるようだが、ダイのほうから近づいてくることはまずない。それでも、マルクがトリスに伝言を頼めば文句を言いつつ伝えてくれる程度には動いてくれる。自由奔放なダイがトリス以外の言うことを聞くとすれば、このマルク以外に例外はない。
「よくわかっているね、マルク」
「苦労人だな、トリス。あの奔放なネズミがお前の苦労に気付いてくれることを願うばかりだ」
「ダイはわかってるよ、多分ね」
「少しもそうは見えないけどな、お前がそういうのならそうなんだろう。おれなら首輪と鎖でも付けてしまいそうだ」
ダイがこれまで仕出かしたことを思えば、そうしてしまうのが普通だとマルクは思う。
学校の教材を片っ端から引っかいてみたり、見本にしている稀少鉱物を噛み砕いてみたり、校内に住まうネズミを総動員して生徒を驚かせてみたり、温室で育てている薬草を食い散らかしてみたり、と普通の召喚獣は決してしないような悪戯を数え切れないほどしでかしてきた。
そのたびに謝罪してまわるトリスは、さっさとあのネズミを魔界へ還してしまえという言葉を何度もあびせられていた。けれど、トリスは決して肯首しない。ダイの後始末は引き受けても、送還することは絶対に受け付けないのだ。
ふと、教室の扉が開く音がする。
二人が反射的に振り返ると、そこにはトリスと同じくらいの少年が立っていた。
「召喚獣の講義はこの教室ですか?」
「そうだけど、きみは?」
「はい。本日からこの講義を受けることになりました『青銀の夜明け学校』三年のノット・ハウライトです。先日の授業で召喚獣を持ちました。よろしくお願いします」
マルクの質問に答え挨拶すると、ノットは二人の傍に寄る。
「ああ、宜しく。おれはマルク、これはおれの召喚獣のモン・スー、風魔鳥だ。こっちはトリス、召喚獣は連れてきていないが鉄鼠のダイっていうのがいる。きみの召喚獣はなに?」
「ノットと呼んでください。ぼくの召喚獣はこいつです。ヤグといいます」
彼の手の甲にへばり付いている小さな蜥蜴を見て、マルクは小さく口笛を吹く。
「凄いな、これ火蜥蜴だろう? 今は小さいから中級だけれど、育てば上級にもなる」
「風魔鳥も珍しいですよね。中級魔族でもなかなか出てこない希少種と聞きます」
「魔族に随分詳しいんだね。ぼくと同じ年でしょう? 独学?」
トリスの言葉にノットは微笑を返す。
「ええ、ぼくは召喚士を目指しているんです。だから、あなたとも会って見たかった。最年少にして最初の召喚魔法陣で魔族の召喚に成功したトリスティン・クロソライト。お会いできて光栄です。よろしく」
「トリスでいいよ。こちらこそ、よろしく」
ノットが差し出した手を、トリスは握り返した。彼の笑顔に答えるように歓迎する微笑と共に。だが、マルクは二人の姿を交合に眺めて、少し考えるように視線をそらした。
やがて現れた教師に改めてノットを紹介され、その日から一緒の講義を受けることになったノットは、教師も顔負けなくらいに魔族に関しての知識を持っていた。
魔族の特性や生態については講義の必要性がないくらいに勉強してきたようだった。
「召喚士を目指しているので、このくらい当たり前です」
教師に褒められても驕ることなく真剣に講義を受ける。
「随分肩に力の入った新入りだな」
マルクにしては珍しく多少の皮肉交じりな言葉だった。
「熱心でいいじゃない。ぼくたちもあのくらい勉強しないといけないのかもしれないね」
「おれは召喚士志望じゃないんだよ。適度で十分さ」
肩をすくめてマルクは会話を打ち切った。
いつもは教室内を飛び回ったり、教師の頭に止まって授業の邪魔をしたりするモン・スーも、マルクの肩で小さく蹲っていた。
召喚獣は召喚士に忠実だと言われている。モン・スーの態度は見慣れない存在を警戒しているようにも、マルクの心情を如実に表しているようにも見えた。
その週末、トリスはエカティの家の隣にある自分の家に戻っていた。
月に二度は空気の入れ替えと掃除のために、帰宅する。現在の保護者であるエカティの両親も、隣の家にいるトリスを案じるほど過保護ではない。徐々に自活するための良い準備期間だと思っているのか、夕食さえ共に済ませば「隣に行って来ます」という言葉で送り出してくれる。
その夜、ダイがお嫁さんに迎えたエリザベスを連れてきてトリスに紹介することになっていた。トリスはダイの要求通りカゴいっぱいのりんごとチーズを用意して彼らが来るのを待っていた。
不意にドンという衝撃音がする。振り返るといま机の上に着地しましたという格好でダイが現れた。
「トリス、いいか? ベスを連れてきたんだ、会ってくれるよな」
天井から突然落ちてきたダイは、ふさふさの髭を震わせて目を細める。笑った顔は愛嬌があると思うのだが、トリス以外の前ではダイが笑わないので、その共感を得られる相手がいない。
「もちろんだよ、待ってたんだ」
キーキーともチュウチュウともつかない泣き声をダイが発すると、彼が落ちてきたであろう天井の小さい穴から白いネズミが顔を覗かせた。
「あのさ、恥ずかしがりやであそこから降りてこられないんだって。それでもいいかな?」
「いいよ。ダイじゃあるまいし、あの高さから降りるっていうのは普通のネズミには無理だろうからね。それに彼女、人間は怖いだろう?」
「え? トリスはいつの間にネズミ語がわかるようになったんだ?」
「全然わからないよ。でも、想像はつくからね」
ばつが悪そうに髭をなでるダイに、トリスは笑う。
「こんばんは、エリザベス。ぼくがダイの召喚士、トリスだよ。よろしくね。これ、結婚祝いなんだけど、受け取ってもらえるかな?」
カゴいっぱいに詰め込まれたりんごとチーズを見て、エリザベスは小さく鳴いた。
「ありがとうって。ダイの主人が優しそうな人間で安心したって言っている」
通訳するダイは小さな手で顔をひっきりなしにかき、まるで照れているように思えた。
「そっか。こちらこそダイのことよろしくね」
「なっ、なっ、トリス。このりんご、おいら食ってもいい?」
「いいけど、持って帰って二人で食べなよ。新居を探してたんでしょう? 結局、どこに住むことにしたの?」
「ここ。この家の屋根裏に住むことにしたんだ。ここならトリスのところにもすぐ行けるし、追い出される心配もないだろうから」
初耳だった。そして、ダイの抜け目のなさにも驚いた。確かに妙案ではある。
「そういうことは最初に言ってよ。驚くじゃないか」
「驚かそうと思ったんだもんさ。びっくりした?」
「うん、びっくりした。よく考えたよね。ちょっと、ダイ。りんご食べるまえに、エリザベスにチーズ運んであげなよ。彼女、見ているだけの状態になっちゃうよ」
「お、おう。いま、そうしようと思ってたんだよ」
りんごの前で大きく口を開けていたダイは、トリスに言われてから慌ててチーズに手をかける。
「トリス、おいらをあの穴に放り投げてくれ」
自分が落ちてきた天井の小さな穴をさして、ダイは無茶苦茶な要求をする。
「間違って天井板にぶつけても、文句言わないならやってあげるけど」
「やっぱり、いい。自分で行って来る」
「いってらっしゃい」
天井の穴から覗いていたエリザベスが小さく鳴いた。トリスは彼女が笑ったのだとなんとなく思った。
その夜、ダイはトリスの枕元でベスの自慢話に花を咲かせていた。
ベスがこうしてくれた、ああしてくれた、と髭を震わせ尻尾をぴんとたて、ダイの話は尽きることがないように思った。だが、一通りの話が終わったのか話疲れたのか、深夜にちかい時刻にダイの話に休息ができる。
エリザベスは人語を解さないのでこの場は遠慮し、運ばれたチーズと共に屋根裏に作った巣穴で先に寝ているとダイは言っていた。
「そうだ、ダイ。来月の『黄金の夜明け学校』で行われる召喚獣講義に、ダイも一緒に来て欲しいんだ。今日、新しい仲間ができたんだよ。お互い、見知っておいたほうが良いと思うんだ。一回は同行して欲しいんだけどな。彼も会いたいって言ってたよ」
「ふーん、彼ねえ。なんてヤツ? マルクやモン・スーはなんて言ってた?」
「召喚士はノット・ハウライトって言って、ぼくと同じ『青銀の夜明け学校』の三年なんだって。先月召喚したらしいよ。召喚獣は火蜥蜴のヤグ。マルクは別に何も言ってなかったし、モン・スーも特には。そういえばおとなしかったかな。でも、モン・スーは風属性だし、火蜥蜴は火属性だし、基本的に相性はそれほど良くないよね」
「まあな。火と風じゃおいらの土より互いに相性悪いかもな。でも、水よりはましなはずだろう?」
「それはそうだけど、水属性の子がいないんだから比べようがないよ。でも、珍しいね。ダイが他人の反応、気にするなんてさ」
トリスに指先で頭をさすられ、ダイは困ったように髭をなでる。
「おいら、自分で言うのもなんだけど、魔族のなかじゃ下級中の下級な種族なんだよね。おいらに会ってみたいっていうこと自体、なんか怪しいと思う。普通さ、魔族って自分より下だと思っているヤツには興味ないもんなんだよ。人間だって、下級より中級、中級より上級の魔族を召喚したいって思ってるじゃん。あ、トリスは別だよ。おいらみたいなのでもちゃんと召喚獣として扱ってくれてるし、信用してるよ。でも、最初からそんなこという相手は怪しいなって勘ぐっちまうんだ」
ぽりぽりと頭をかきつつ、ダイはトリスを見上げる。
「いいよ。来月はトリスに付き合う。顔見ておくくらいなら問題ねえもん」
頬を膨らませて目じりを下げる。
「ありがとう。無理言ってごめんね」
ダイが他の魔族に会いたがらないことをトリスは知っていた。
下級と呼ばれる魔族が、召喚獣のなかで受ける扱いを知っていたから、無理強いすることは苦しい。
指先でダイの頭をそっとなでる。緑の大きな瞳が細められ、トリスの指先にダイの微かな体温が伝わってきた。
この小さな召喚獣は、本当に簡単な初級の魔法陣から這い出るようにやってきた。
教科書通りの簡単な法陣を書いただけだったトリスは、突然光り輝いたそれに目を見張った。教室内の誰もが驚いており、教師が対応する間もなく、小さなネズミの姿が魔法陣のなかに現れた途端、光が消える。
召喚が成功したことは見てわかった。それが下級と呼ばれる魔族であることもなんとなくわかった。体が小さかったからではない。さほど魔力を感じなかったからだ。
「お前が召喚士か? おいらのこと、魔界に戻さないでくれ」
第一声は懇願という悲鳴に近い叫びだった。
「特殊能力とか魔力とかないけど、絶対にお前のこと裏切ったりしないから。おいら、どうしても召喚獣になりたいんだよ。一族の悲願なんだ」
小さな手を必死ですり合わせ、トリスを見上げる緑の瞳は真剣そのものだった。
「トリスティン・クロソライト、君は生まれてはじめての召喚陣で召喚に成功してしまったようだ。どうするかね? 君が望むなら、私がこの魔族を送還する手助けをするが」
困惑した教師の顔が傍らにあった。トリスは教師を見上げ、もう一度机の上の小さなネズミに視線を落とす。
「イヤだ。おいらの一族にはどうしても召喚獣が必要なんだ。使い魔じゃダメなんだよ。頼むからこのままおいらのこと、この世界に置いてくれよ」
「こんな下級魔族、なんの役にもたたないと思うがね」
召喚獣は一人一体。それは絶対的な規則だった。
どうせ召喚術を行うのなら、下級より中級を、中級より上級の魔族を望むのは召喚士として当たり前だと言われていた。
召喚したものが召喚された魔族の名を口にするまで、召喚獣は陣から出られない。契約が成立していないからだ。教師が手にしていた杖をトリスの魔法陣に向けたときだった。
「いいよ、ダイオプティース。今日から君がぼくの召喚獣だ。よろしく」
それはダイを拒んでいた世界が彼を受け入れた瞬間だった。教師が向けていた杖の威力は効果を失う。そして、誰もがトリスに注目した。
召喚に成功したとはいえ、それは最下級の魔族。どうみても召喚に値する魔族ではない。
差し伸べられたトリスの指先に、ダイは涙を流しながら頭をこすり付けた。それが自由に動く体で最初にした二人だけの契約だった。
下級魔族は知能が低いと言われている。
実際、ダイは中級魔族や上級魔族ならしないようなことを平気でしていた。
学校の標本に悪戯したり、温室の薬草を食い散らかしたりというのは有名であるが、トリスの教科書を勝手に持ち出して外で広げてみたり、時計の振り子につかまって降りられなくなったりという騒ぎは日常茶飯事だった。
トリスはそのたびに根気よく「してもいいこと」と「絶対にしてはいけないこと」をダイに言い聞かせていった。
トリスの言いつけを守り、ダイが同じ悪戯を二度するということはなかった。
それでもダイの悪名高いのは、最年少の少年が最弱の召喚獣を持ったという、駆け巡るように広がってしまった噂のせいでもある。
それには当然、トリスに対する嫉妬や偏見も混じっていたことだろう。ダイに対する嫌悪感があったことも否めない。才能ある若者が下級召喚獣を持つということは、召喚士として限界が見えてしまっているということでもある。もちろん、召喚獣を取り替えることは可能だ。それには大前提として、現在の召喚獣であるダイを魔界へ送還することが絶対条件となる。
トリスはそれを拒み続けた。
どれほどダイのせいで頭を下げることになっても、迷惑を被っても、彼は送還の件だけは笑って答えず、絶対に肯首しない。
今のトリスなら、上級魔族の召喚も可能だろうと噂されている。おそらく、噂ではなく真実だと思う人間は多い。
マルクも同じ若年召喚士としてその可能性を感じていた。
その日、久々にダイを連れてきたトリスをみて、マルクは正直なところもったいないと思ってしまう。
マルク自身は召喚士というものに憧れはない。ただ、トリスの才能が垣間見えるとき、ダイではトリスの召喚獣として物足りないと感じてしまうのだ。
それを口にするほど野暮ではない。彼らの仲のよさは折り紙つきで、それだけは誰も否定するものがいないからだ。
「ダイ、嫁さんもらったんだって? 今度、おれらにも紹介しろよ」
「ヤダよ。マルクなんかに見せるのもったいない」
つんとそっぽを向くネズミに、マルクは笑う。
「なんでさ、トリスには紹介したんだろ? ケチケチするな、減るもんじゃなし」
「減るもん。絶対磨り減る」
「ほう、じゃあ、折角用意したこの結婚祝いもないほうがいいわけだな? そうか、もったいないから、モン・スーにでもくれてやったほうがいいか」
聞こえよがしというか、これ見よがしに持ってきたりんごを掴み、マルクは自分の召喚獣の前に差し出した。モン・スーも主人の意向を汲んで、大きく口を開けたままダイの様子を見る。
「えっと、祝いの品だけもらってやってもいい」
慌てて手を振るダイに、マルクはにやりと笑う。
「見せたら磨り減るんだろ?」
「見せないもん。でも、りんごはよこせ」
小さな手を差し出しふんぞり返るダイを、マルクは指先で弾く。
「ください、だ。言えたらやるよ」
「ダイ。こういうときは素直に言ったほうが良いと思うよ?」
トリスの言葉が効いたのか、ダイは渋々「ください」とマルクにささやく。
ダイにりんごの美味しさを教えたのはマルクだった。モン・スーの餌として持っていたりんごを、ダイにもお近づきのしるしとして差し出したのがはじまりだ。モン・スーは風魔鳥で、本来ならダイの天敵でもあるが、同じ召喚獣として他人の召喚獣を襲うことはない。そしてモン・スーも小さなネズミのダイよりもマルクがくれるりんごのほうが好物だった。
「しょうがねえな。祝い事だし、大目に見てやるよ。で、嫁さんの名前は?」
「ヒ、ミ、ツ」
「エリザベスだよ。白いハツカネズミ」
「トリス、なんでバラすんだよ」
ダイは自分の主人にくってかかる。だが、トリスにあっさりと言い負かされてしまう。
「お祝いもらって内緒にするのは失礼なんだよ。マルクが笑って許してくれる間に、譲歩できることは譲歩するの。なにも彼女をここに連れて来いって言ってるわけじゃないんだから」
「あーあ、先にクギさされちまった。連れて来いって言おうと思ってたのにさ。良い主人を持って良かったな、ダイ。モン・スー、これからは白いネズミは食べるなよ。ダイの嫁さんだったらおれが後味悪いからな」
モン・スーは小さく鳴いて主人に答える。風魔鳥は鳥を操る。モン・スーが約束したのなら、白いネズミは鳥にだけは襲われる心配がなくなったということだ。本当の結婚祝いはこちらなのかもしれない、とトリスは思った。
「今日は賑やかですね」
ノット・ハウライトの声がして、トリスとマルクが振り返った。
「ああ、うるさかったかな。ダイを久しぶりに連れてきたんだ。結構お喋りだからね、ぼくの召喚獣は」
「噂の鉄鼠ですね。ぼくにも紹介していただけますか?」
ノットの笑顔に、トリスも答える。
「これがダイオプティースだよ。ダイ、こっちが召喚士のノット、ノットの召喚獣、火蜥蜴のヤグ」
トリスは手のひらにのせたダイをノットの前に差し出して紹介する。
「よろしく、ダイ」
ノットが声をかけるや否や、ダイはトリスの襟首の中に駆け込んで隠れてしまう。トリスが手を伸ばしても、絶対に出てこようとはしなかった。
「ちょっと、ダイ? おかしいな、そんなに人見知りしないんだけど、慣れてないだけだと思う。ノット、気を悪くしないでくれると嬉しいんだけど」
「とんでもない。紹介してもらって良かったよ」
ノットは笑顔で答える。
小動物ほど本能的に危険を察知する能力が備わっているという。この場にダイ以上の小動物はいない。現在の大きさではヤグが一番小さいかもしれないが、潜在能力はダイよりはるかにヤグが上回る。
終始無言で眺めていたマルクは、どうしてか嫌な予感がしてならなかった。
|
|