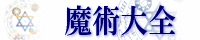 〜最下級召喚獣〜 1 〜最下級召喚獣〜 1 |
小さな影が廊下を駆ける。
それは人足よりも少し早い速度で、目指す場所までの最短距離を迷いなく辿っていた。
外気は冬の厳しさから抜け、芽吹きの暖かさを増す。
もうじき卒業、そして入学の時期をむかえる。今はただ、卒業認定試験に励む生徒が多い。
ここは『青銀の夜明け学校』と呼ばれる場所になる。
卒業資格はプラクティカスという水属性の資格を取ることだ。
三年の教室では五月の最終試験に向けて、全員が殺気立つほどに神経を尖らせていた。
教室のドア下部に小さく設けられている窓がある。大きさは猫が出入りするのにちょうど良いくらいのものだ。そこから教室内に走りこんだ小さな影は、目当ての人物をすぐに見つけた。
「トリス! きいてくれよ、おいら、やっとベスに振り向いてもらえたんだよ」
窓際に座る一人の生徒を目指し、猛進の勢いを緩める暇もないまま飛びついた。呼ばれ飛びつかれた少年は「うわっ!」と叫びながら椅子から落ちた。飛びつかれた勢いが強かったことと、咄嗟のことで判断が遅れたせいだ。
緊張に溢れていた教室内は瞬時静まり、否応なく視線は小さな影が飛びついた生徒に集中する。
魔術師候補生は、時として技の成熟度が他者より秀でたものがまぎれている。それは特技、とでも言うのだろうか。万遍に滞りなく熟練するのが好ましいのだが、人間である以上、得手不得手というものが存在し、それは時として課題過程以前に本人の意思すら関係なく術が発動した結果というものがついてまわる。
このトリスティン・クロソライトという生徒はその一例である。
召喚術という授業の最中に彼の魔法陣から出てきてしまった召喚獣がいた。
本来、魔界から召喚獣を呼び出す召喚術というのは『青銀の夜明け学校』より上位にあたる『黄金の夜明け学校』卒業時に卒業課題として出される高度な術だ。召喚獣を持つということは、魔術技術の基礎をマスターしたという証でもある。
召喚獣は召喚士が相手の名を受け取った時点で人間界の住獣として正式に認められる。それは奇妙な偶然でトリスの召喚獣となったダイオプティースにも同様に与えられた。
小さな灰色のネズミが首に巻く赤いリボンには、刺繍されたペンタグラム(五芒星)が見える。これが異界である人間界で、ダイの存在を確実なものにしてくれているのだ。
一見、ダイの姿は普通の鼠に見える。だが、よく見ると鉄の牙と爪を持った鉄鼠と呼ばれる魔族であることがわかる。そしてなにより、普通の鼠は人語を喋ることはない。
「ダイ? あのね、すっごく喜んでいるのに悪いんだけど、ぼく、まだ授業中なんだ。休み時間になったらゆっくり話を聞くから、今は静かにしてもらえると嬉しいんだけど」
自分の胸部にしがみつき、尻尾を勢い良くふりながら緑の瞳を輝かせるダイの顔をみて、トリスは穏やかに微笑む。
「おうっ、そうか。そりゃ悪かったな。おいら、ここで待ってても良いか?」
「静かにできるなら良いよ。みんなに迷惑かけないって約束できる?」
「もちろんだ!」
「そう、じゃあ鞄の中に入ってて。授業が終わるまで動かずにじっとしていてね。喋っちゃダメだよ」
「了解だぜ」
機嫌よくトリスの鞄に入り、ダイは小さく蹲った。トリスは立ち上がると「授業を中断させてしまってすいません」と頭を下げる。
教師もクラスメイトにも見慣れた光景だった。
元気が良すぎるトリスの召喚獣は、決して扱いやすいものではない。ましてや能力の低い下級魔族である。自らの召喚獣が引き起こした不祥事のために、トリスが何度も頭をさげるのを見ていた。
ただ不思議なのは、トリスがその召喚獣を魔界に送り返さないことだ。
呼び出した召喚士のみが召喚獣を送り返すことができる。そしてダイを偶然呼び出した当初ならともかく、今のトリスにならダイを魔界へ送り返すことは容易であるはずだった。
召喚獣は一人一体。ダイがいる限り、トリスが新しい魔族を召喚することは許されない。ダイを偶然呼び出してからの二年間で、トリスの召喚術は群を抜いて素晴らしいものになっていた。
「認定試験間近のこういう時期だからこそ、トリスティン、あなたの召喚獣をきちんと御してほしいものです。では、授業を続けますよ」
教師は苦言を呈する。だが、トリスは「すいません」と言うだけで微笑んでいる。
ダイの迷惑行動を詫びることはあっても、決して魔界へ戻すということだけは言わないのだ。この二年間でそれだけは学校中に知れ渡っていた。
授業終了の鐘とともに、教室内にもざわめきが広がる。
クラスメイトが肩の力を抜いたことを確認してから、トリスは鞄を開いて呼びかける。
「ダイ、もう出てきてもいいよ」
召喚士の呼びかけにダイは顔を上げ、トリスの肩まで駆け上がる。そこがダイの定位置だ。
「ねえ、トリス。この迷惑なネズミ、さっさと魔界へ還しちゃいなよ。トリスならもっと上級魔族だって呼び出せるでしょ? こんなのがいるせいで上級が呼び出せないなんてもったいないよ」
「そんなことないよ、エカティ。いまダイを魔界へ還したら、ぼくが召喚獣を呼び出せるのは早くても三年先になっちゃうよ」
後ろの席の幼馴染にトリスは答える。エカティはうんざりしたような顔でダイを眺め、「どうしてこんなのが」とぶつぶつ呟いてはいたが、それ以上は言わず顔を背けた。
だが、反撃は違うところからおきた。
「うるさいやい、そばかす女。おいらを魔界へ還すかどうかはトリスが決めるんだ。お前なんかが口出しすることじゃないやい」
トリスの肩で、ダイは尻尾を振りつつ片手でぺしぺしと自分のお尻を叩いてエカティを挑発する。そばかすをエカティが一番気にしていると知った上での言葉だった。
「なんですって、この迷惑ネズミ。だいたいね、あんたトリスの召喚獣だっていうなら、もうすこし主人の役にたってみなさいよ。いつだって騒ぎおこしてトリスに謝らせてばっかりいる役立たずのくせに」
「おいらが迷惑かけているのはトリスにだけだ。お前になんか迷惑かけてないやい」
「そこ、威張るところじゃない。少しは反省しなさい」
今にも掴みかからんばかりに近づいたエカティの鼻を、ダイは軽く引っかいた。赤い筋が三本、血がにじむほどではないが、今日中には消えないだろう程度のあとがエカティの鼻頭につく。
「ダイ、ダメだよ。人間を傷つけちゃ」
人間を傷つけたら召喚獣は強制帰還させられる。トリスはダイを叱ってからエカティの傷を治そうとした。だが、エカティには「自分で治せる」と拒絶される。そして、手を出した当の本人は全く気にしていなかった。
「傷なんかつけちゃいないぜ。血が出ないように手加減してやったんだからな。一時間もすれば消えるかわいいもんだ」
「あら、そう。どうせなら血が出るように傷つけてくれたらよかったのに。そうすればトリスに憑く性悪魔族を簡単に魔界へ転送できたっていうのに、気が利かないわね」
自分の鼻を押さえつつ、エカティの鋭い眼光がダイを見つめていた。
「なんでおいらがお前に気を利かさなきゃならなんだよ。おいらが気を利かすのはトリスにだけだ。一緒に暮らしているから召喚獣を操れるなんて思うなよ」
「気を利かすどころか、役に立ったことないくせに威張ってんじゃないわよ」
トリスの肩口で一触即発の危機がおきていた。
彼は指先でダイの頭をはじく。
「ダイ、まずちゃんとエカティに謝って。強制送還になりたいの?」
「そんなのイヤだよ。でも、このうるさい女が最初にケンカ売ってきたんだぜ?」
「ケンカ売られたらなんでも買っていいわけじゃないよ。手を出したのはダイが悪いんだから、ちゃんと謝る」
頬をめいっぱい膨らませて不満を表していたダイだが、トリスの言うことには渋々従った。
「……今日のところはこのくらいで許してやるぜ」
「ダイ、ごめんなさいは?」
「………………ごめん」
のどの奥でぐるると唸るように、ダイはトリスの求める言葉を吐き出した。
「ごめんなさい、エカティさん、どうか許してください。くらいは言えるようになってちょうだい。クソネズミさん」
形勢が変わったのを見て、エカティはダイの前でにやりと笑う。それはきっと、彼女の鼻頭にある赤い三本筋がなければもっと様になっていたことだろう。
「イヤだ。おいら、お前嫌いだもん」
「あら、私もあんたが大嫌いよ。変なところで気が合うわね」
「合ってねーもん、ちっとも。欠片も、これっぽっちも」
「口の減らないネズミね」
「口は一つだ。減ってたまるか」
エカティの怒りが再燃する前に、トリスはダイを連れて教室を飛び出した。
この二人の相性が最悪なのは、ダイを召喚した直後から全く変わらない。
「二人とも、もうちょっと仲良くなれたらいいのにね」というトリスの呟きは「真っ平ゴメンだ」というダイの拒絶にあう。多分、エカティに言っても同じ答えが返ってくるのだろう、とトリスは思った。
|
|