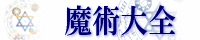 〜最下級召喚獣〜 6 〜最下級召喚獣〜 6 |
「なぜ……」
早朝の訪問者を前に、彼は呟く。
腹立たしいのか情けないのか、怒っているのか安堵しているのか、自分の感情も定まらないままに訪問者を見上げた。
「それをおれに問うのか? 答えて欲しいのか?」
口元には笑みを浮かべているのに、その眼光は鋭く、容赦のないえぐるような眼差しを向けられて彼は戸惑った。だが、すぐに気を取り直して取り繕う。
「なんのことかぼくにはわかりませんが、訪問の理由を尋ねてもよろしいでしょうか?」
「理由、ね。聞きたいのなら教えてやる。お前の召喚獣はおれが責任を持って審問会に差し出した。召喚獣は他人の召喚獣を襲ってはならない。ヤグはダイに火炎を吐いた。現場を見た以上、見過ごすわけにはいかない。お前の召喚獣は暫くは戻ってこないと思え。それだけだ」
じゃあな、と手を上げて踵を返した彼を呼び止める。
「マルク。カイアストライト家はクロソライト家を支持するということですか?」
「いいや、おれの独断だ。三男坊ごときに家名は関係ない。でもなノット、無関係の人間を巻き込むな。それだけはおれが許さない。何度でも邪魔してやるよ」
「クロソライトを庇護するのであれば、エルバイト家も同罪です。ぼくはクロソライトの家名を潰すために産み育てられた、それはあなただって知っているはずだ。カイアストライトの名を持ってして知らないなんて言わせない」
「ライト」の家名を持つ者は、召喚士を多く排出する。だから、必然的に各家の内情は漏れ聞こえてくるものだ。
カイアストライト家は現召喚士の筆頭。ハウライト家も召喚士の一族、そして、クロソライト家も召喚士として知られた家名だ。
「知らないとは言わねえよ。けれど、それはお前の家の問題だ。クロソライト家は罪に問われない。あの日、そう決まったんだ」
頭一つぶん高い彼の威圧感は、ノットの反論を押さえ込むのに十分だった。
「お前が正々堂々とトリスに挑戦状叩きつけるっていうのなら、反対もしないし邪魔もしない。むしろ応援してやるよ。けどな、召喚獣を御しきれていない今のお前じゃトリスには敵わない。高位の火蜥蜴をもってしても、正当な召喚獣である以上、最下級の鉄鼠であれ負かすことはできない。お前はよくても魔族にしてみたら屈辱の極みだ。それにお前、ヤグを召喚するために一体なにを差し出した? 全うな方法じゃないはずだ。違うか? だから、ヤグは根本的なところで召喚獣として不完全だ」
定められた召喚獣のくびきを自ら壊す行動をすること自体、召喚主を軽く見ている証拠だ。例えそれが召喚主の命令であったとしても、正当な方法で召喚された魔族は人間界の理を破ったりはしない。
ヤグがダイを襲った。それだけで理由は十分だった。
ハウライト家がクロソライト家を憎む理由を、マルクも知っていた。
その雪辱のために、身篭ったばかりの子供の性別を秘術で替えたという話も有名だ。
そしておそらく、トリスはクロソライト家とハウライト家との過去を何も知らない。教えられる相応の年齢になる前に身内が死に絶えているのだ。ノットに対する態度でもそれが伺えた。トリスの暢気な挨拶や無防備な対応は、クロソライト家への恨みを植えつけられるように育ったノットにとって、火に油を注ぐような行為であったろう。
トリスやノットが悪いわけではない。
召喚士を多く排出する「ライト」の家名を持つ一族なら、誰でも憧れる力をクロソライト家は手にしたのだから。それは確かに、ハウライト家の努力を犠牲にするものではあったけれども、先達の判断が間違っているとマルクには思えなかった。
「過去の恨みをひきずっている家名に潰されるなよ。そんなことのために頑張ってきたわけじゃないだろう?」
知識だけでは魔族を従わせることは出来ない。
ノットの召喚術に関する知識は深いが、積み重ねる努力という才能なくして法陣は反応しないし、魔族は答えてくれない。
魔族の忠誠を得たクロソライトの名を持つもの以外、それは必須であるはずだった。
「……ぼくは、何も知りません」
「別にいいさ、今はそれでも」
小さな羽音が聞こえる。いつの間にか彼の肩に止まった青い小鳥が、小さく鳴いた。
「卒業認定試験か。トリスが実力で伸し上がってくるのなら、お前も自分の実力で伸し上がって来い」
「クロソライトの召喚獣があれば実力など関係ない!」
「ダイが大怪我でしばらくは動けないそうだ。トリスは普通に試験を受けて上がって来る。ヤグがいないお前と条件は一緒だ。実力だよ。おれは二人が揃って『黄金の夜明け学校』に来るのを待ってるからな」
訝しげに視線をあげたノットに、彼は快活に笑んだ。
実際、ノットの術精度には抜きん出たものがある。
エルバイト家の娘を昼前に発見しながら深夜まで助けられなかったのは、ノットが厳重に張り巡らせていた封印と防御のせいだ。マルクはそれほど熱心な魔術師候補生ではなかったため、どうにかこうにか力技で破って近づいたのだ。
最後は、トリスの力が内部から全て壊してくれたおかげなのだが、そんな余計なことまで言う必要はないだろう。
「言ったろう? 正々堂々の勝負なら邪魔しないし応援してやるって」
目の前に伸びてきた指先が、ノットの額を軽く弾く。
「しけたツラすんな。お前も試験頑張れよ」
恨み言のこもらぬ純粋な励ましの言葉というものを、ノットはその時初めて聞いた。
『黄金の夜明け学校』の入学式で、その騒ぎはおこった。
悪びれる様子もなく、トリスとエカティ、そしてロゼットの前に現れたノット・ハウライトは、笑顔で親しげに近寄ってくる。
「やあ、ひさしぶりだね、きみたち」
「あんた、よくその顔、私の前に出せたわね」
「そうだ、そうだ。いいぞ、そばかす女」
トリスはエカティとダイの意見が一致するのを始めてみた。目の前のノットより、こちらのほうがずっと驚きだった。
「ぼくの顔はきみよりずっと評判が良いと自負してるんだけどな」
「自惚れてんじゃないわよ。大体、あんたのおかげでロゼットは怪我するし、私は試験ギリギリまで怖い思いさせられたし、このネズミだって大火傷したんだからね。少しは謝罪するとか頭下げるとかいう気持ちはないの?」
ロゼットは怪我を考慮され病室で、エカティはぶっつけ本番の覚悟で卒業認定試験にのぞみ、晴れて昇級することができたのは実力故にだ。結果がでるまで、二人は神頼みというこれまでにしたこともない方法に縋り付くほど不安を抱える日々を過ごしたのだ。
「済んだことをいつまでも覚えているのは不幸だよ? なんなら忘れさせてあげようか?」
「結構です。いいえ、むしろ絶対忘れたくないの。余計なことしないで頂戴」
ロゼットの傷害事件も、エカティが行方不明になった事件も、結局は証拠不十分という形でノット・ハウライトへの処罰はなされなかった。証拠となる鉄鼠を魔界へ送還してしまったのがトリスであったため、二人は渋々ながら事を穏便に済ませる方法を選ぶしかなかった。
ただ、マルク・カイアストライトに発見されたヤグは、ダイオプティースへ火炎を放った現場を目撃されたため、半年の謹慎という処分を受けることになった。現在は魔族飼育室という場所でノットと隔離され暮らしている。
「ヤグがいないと、毎日つまらないんだよね」
ノットは全然反省の色もなく、むしろ友好的な態度が不気味でさえある。
「ちょっと、あんたなんで私等についてくるのよ。あっちに行きなさいよ」
手で追い払う素振りをするエカティに、ノットは笑った。
「えー? 敵にするのがイヤだな、と思った相手とは、友好関係を築いたほうが前向きで建設的だと思うんだけど」
「そんな自分勝手な前向きと、捻じ曲がった建設的な意見は参考にならないわ」
ロゼットが反論する。痛恨の一撃にノットの顔が苦笑で歪んだ。
「もう良いじゃないか、今日くらいは。折角の入学式なんだし……」
周囲の注目が気になり始めたトリスが仲裁に入るが、おもいきり女性陣の反論にあう。
「良くないわ。ちっとも良くないのよ、トリス。こいつとだけは仲良くしなくても、誰にも文句なんて言わせないわよ」
「そうよ。こういうことは最初が肝心だもの」
だが、とりなされた本人はそうは思わなかった。
「結構話せるじゃないか、トリスティン・クロソライト。流石は我が好敵手と認めた男だ。そうだよな、この場合、男女比率が同等のほうが周囲に対する見栄えも良いに違いない」
肩を抱くようにトリスに近寄ったノットを、エカティが邪魔をする。
「トリスに近寄んないでよ、この根暗男。トリスにあんたの根性悪いところがうつったら大変だわ。トリス、早速保健室に行ってこいつに触られたところ、消毒しましょうね」
エカティがトリスの腕を取り、入学式の会場とは別方向に歩き始める。
「そうね。男女比率も見栄えも、私は気にしないわ」
ロゼットもその背を押すように流れに逆らう。
「エカティ、ロゼットも。今はいいから入学式の会場に行こうよ」
その時、周囲から浮いたこの集団に声をかけるつわものがいた。
「おーい、トリス、ダイ。よく来たな。エカティも元気そうでなにより。お、ノットも一緒か」
校舎の屋上から手を振るのは、マクル・カイアストライトだ。
暢気に呼びかけて手招きする。
「サボるのなら、ここの屋上は最高だぜ。招待するぞ」
小さな青い鳥が声高に鳴く。掃天は高く、雲ひとつない。
「マルク、久しぶり。ねえ、新入生でもそこまで行っても良いの?」
「教室じゃないんだ、遠慮するな」
エカティに答えるマルクの声もまたよく響く。
「ロゼット、彼が私のこと助けてくれた人なの。ちょうど良いから紹介するわ。一緒に行きましょうよ」
「そうね。男女比率に拘るのなら、エカティの恩人のほうを歓迎するわ」
女性二人は入学式よりも恩人の招待を優先する気満々だった。
「ノット。男女比率を気にしないのなら、きみも一緒に招待されようよ」
トリスはノットに手を伸ばす。
「えー、おいらそいつ大嫌いだ。絶対反対!」
耳元でダイの抗議が響く。一瞬、目を軽く見開いたノットは、次の瞬間にはふてぶてしい笑顔に戻る。
「そうだね。先輩の招待を無碍にするもんじゃない」
トリスの手を叩き、ノットは先に向かった女性陣の後を追う。
あれが彼なりの精一杯の謝罪の形だったのかもしれない。
耳元でがなりたてるダイと先を行くノットを見比べて、トリスは噴出した。
誰かに似ていると思えば、この小さい召喚獣の反応にそっくりなのではないだろうか。
「ねえ、ノット。一つだけ良いかな?」
「なに?」
不意に声をかけられて、ノットは昇りかけた階段から素直に振り返る。
「君の父上に伝えておいてよ。ぼくはクロソライトの当主として、父のしたことを詫びるつもりもなければ、ハウライト家に配慮する気もない。ぼくが父でも同じことをしたと思う」
「――お前」
「全部知っているよ。ぼくはこれでも正式に当主就任したんだから。だから、君の怒りを受ける義務もある。そうだろう? でも、エカティやロゼットを巻き込むのは違う。ベリル家のことは別問題だ。だから次はない」
真摯なトリスの視線を受けて、ノットは息を呑んだ。
それまでののんびりした空気は一転し、どこか威圧するような迫力がある。
トリスの父親がノットの父親にしたこと。
それは召喚陣の妨害だった。
召喚獣をより上級の魔族へと願ったハウライトの当主は、召喚陣の精度をあげることに専念していた。そして、それは研究者の助力を得て成功した。孵化直前の竜族の卵に術をかけたのだ。
竜族は道義に反した行いに怒り狂い、召喚陣を壊しにかかったが、術に捕らえられた卵は魔界からは破れない。魔界の異変に気付いたトリスの父親が、その召喚陣を壊し、魔界からかけられていたいくつもの強大な竜族の力をその身に受けることになった。
それは生死をさまよう大怪我だったと聞く。
その行動が魔族でありながら決して召喚に応じないと言われる竜族の友愛と信頼を得るものになった。だから、クロソライト家の家紋には、竜族の文様が刻まれている。その名を持つものの召喚にだけは、いついかなるときも応えるという竜族の盟約だ。
ハウライト家の当主は妨害に怒り、審問会に掛け合ったし、当主会でも問題にしたが、いずれもクロソライト家当主の行動は問題なしという結論がでた。
子守唄のように聞かされてきた過去の出来事は、ノットの記憶に鮮明な映像を描けるほど繰り返し聞かされた。だが、父の行為が正しかったのか、と聞かれたなら、頷くことはできないような気もしている。
そして、その高精度の法陣は、当時のクロソライト家当主とベリル博士の共同研究だったと噂されていた。真偽のほどは不明だが、その事件以降、ベリル家の家紋は封印された。
召喚士としてはそれほど高名ではないハウライト家だが、術の精度をあげることで足りないものを補ってきた。その努力は確かに父の功績だと思う。
だが、魔族を召喚することは、お互いを認め合って初めて成立するものだ。孵化直前の卵を召喚するというのは、相手に選ぶ権利を与えない行為だ。なぜなら、孵化した直後に見たものを、彼らは親と思い込むのだから。
「やっぱり、お前――当主の権利振りかざして入学したんじゃ……」
「なんでそんなことする必要があるわけ? だいだい、ダイが元気でいたとしてもぼくの試験に大人しく付き添ってくれるわけないじゃん。これでもちゃんと、勉強していたよ? ねえ、ダイ」
「おう、その通りだ。なあ、トリス。もう行こうぜ、こんなヤツほっといてさ」
トリスの肩で毛を逆立てている鉄鼠は、ことの状況がよくわかっていないようで、ノットの視線をあからさまに無視しただけだった。
トリスはゆっくり歩み寄ると、ノットの肩を軽くたたいて呟いた。
「これから三年間、どうぞよろしく」
トリスの優しい声色が、ノットの胸の奥に冷たいなにかを落とすように染み入った。
謹慎収容されている魔族飼育室で、ヤグは痛み続ける背中の傷に苛立っていた。
魔力が高い魔族ほど、物理的な攻撃には弱い。ましてや下級の鉄鼠に付けられた傷ともなれば屈辱の限りである。
ぼわっと小さな火炎を吐き出した。自慢の長い尾はダイの爪で根元から断ち切られていた。それも更なる苛立ちのもとになる。
コツコツ、と近くの窓がなる。窓の外には見たことのある風魔鳥がとまっていた。
「何用か、風魔鳥の」
彼があの鉄鼠を掴んで飛び去らなければ、ヤグはあの生意気な鉄鼠を焼き尽くすつもりでいた。モン・スーは正当なる復讐の邪魔をした目障りな存在でしかなかった。
「汝、あの鉄鼠を始末し魔界へ戻る気か?」
召喚獣が召喚獣を襲えば、自動的に強制送還となる。モン・スーの意図が見えず、ヤグは更に苛立った。
「それがどうした。我が屈辱を思えば当然のこと。何故邪魔をした」
下位の魔族に傷を付けられたのだ。火蜥蜴の名誉にもかかわる。ヤグは怒りに満ちた視線をモン・スーに投げつけた。
「汝、竜族に刃向かう覚悟はあるか?」
「下らぬことを聞くな。お主にはあるのか。風の主よ」
彼らの思惑はかみあわず、しばらく双方ともにらみ合う形のままでいた。
「では、更に問う。汝の主は汝が火蜥蜴でなくても汝を召喚獣として召したであろうか」
「答えるまでもない。なにが言いたいのだ、風魔鳥」
小さな炎とともにヤグは怒鳴った。モン・スーに届かないことは知っていたが、感情を御することができなかったのだ。
「下級魔族の末端である鉄鼠が、いずれは上級になる火蜥蜴に噛み付くのは、我等が竜族に刃向かうことと同義と我は思う」
「だからどうしたというのだ」
「汝、己が主を信じて竜族に刃向かうほどの忠誠はあろうか。我には未だ明言できぬ」
「あの鉄鼠を見逃せとでも言いに来たか?」
風魔鳥ともあろうものが情けない、と侮蔑する視線を向けたが、モン・スーは動じなかった。
「否。ただし汝の復讐を妨げることはある。それを伝えにきた」
「下級魔族に興味を持ったか」
「否。魔族としては眼中にない。が、召喚獣としては興味がある」
「なにが違うのだ?」
ヤグの訝しげな視線を受け、モン・スーは小さく鳴いた。
「我等は知能が高いと言われている。そのため、主に疑心を抱くこともある。おそらく我は、主に全幅の信頼を待つということはできぬ。主のために命を差し出すことも躊躇う。所詮、人間と魔族は相容れぬ存在である。だが、あの主従は違う。彼等は生き物の本能を凌駕する。汝の背に刻まれた傷のように」
ヤグは答えなかった。モン・スーは気にする様子もなく続ける。
「あの主従関係が、下級魔族の低い知能のせいで結ばれているのか、信頼と言う絆のせいなのか、我は今しばらく観察したい。それだけだ」
微かな羽音が響く。モン・スーが飛び立った窓を見上げ、ヤグは考えた。
問われた答えは全て否だった。迷う隙もなく即座に思った。
最上級魔族である竜族に刃向かうことも、主のために死ぬることも、全幅の信頼を置くことも。そして、おそらく主とてヤグが火蜥蜴でなければ召喚獣としてこの世界に招くことはなかっただろう。
だから気付いてしまった。あの脆弱な鉄鼠が咄嗟に向かってきた覚悟の大きさに。
「どうせ阻まれるのであれば、無駄な努力というものか」
あの風魔鳥は小さく見えて成鳥である。火蜥蜴とはいえ、まだ幼いヤグの炎を消し去ることは容易いはずだ。
ぺたり、と床に腹をつける。
背中の傷はまだ痛い。今あの鉄鼠を見かけたら、おそらく遠慮のない火炎を吐きつけてしまうことだろう。それでも思う。
あの召喚士の放つ光は強大で、おそらくはヤグの主を凌ぐ強さを秘めている。彼の光はノットの法陣を消滅させてしまったのだから、おそらくは間違いない。最下級魔族とはいえ、鉄鼠を失えば、あの光を見ることができなくなる。
召喚士というのは不思議なもので、己の召喚獣が居なければその能力すらはかれないのだ。
鉄鼠ごときにあの召喚士は不釣合いだと思うが、観察する猶予というのは確かに悪くない。あるいは、この痛みが消える頃なら、鉄鼠くらい見逃してもいい気分になっているかもしれない。
ヤグはゆっくりと瞳を閉じてこれからのことを考えていた。
|
|